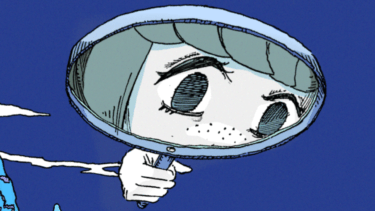「らーめん再遊記」は、「ラーメン発見伝」における主人公のライバルであり、師匠的な側面もあった芹沢さんを主人公としたシリーズで、とても面白いです。
本作における芹沢さんはラーメン屋をセミリタイアした悠々自適な状態で、様々なラーメン関係のトラブルに巻き込まれたり首を突っ込んだりをしています。


「ラーメン発見伝」「らーめん才遊記」「らーめん再遊記」のシリーズにおけるラーメンを巡る話は、ラーメンの話をしているものの、より広く創作一般に適用できるような話がされていることも多いと感じていて、とりわけ現行のシリーズではその側面が強いように感じています。
例えば、ラーメンに関する天才的な発想と創作能力を持っていた男が、自分の天才的な創作ラーメンの能力とその自認にむしろ縛られてしまい、ラーメン屋を続けることができなかったことが露呈するお話は胸に来ました。
漫画家においてもそういうことはよくあり、なまじ新しい感性として評価される漫画を描けていた人が、その後の自分の描くものがそこで評価されたものを超えるものを作れていないのではないかという自縄自縛に陥ってしまい、なかなか新作を作ることができなくなったり、作れても新しくはあるものの奇をてらい過ぎていてエンターテイメント要素が乏しくなってしまったりという事例を目にします。
ものを作るということに関してはラーメンでも漫画でも、おそらくは音楽や小説やゲームやその他色々な物に対しても、共通する問題があるように感じていて、「らーめん再遊記」は創作を取り扱った漫画であるように思いながら読んでいます。
さて、今連載されているエピソードでは「実務家」と「評論家」によるラーメン勝負が始まっており、そこでも、創作における実務家と評論家の違いなどがラーメン勝負の中で見えてくるのではないかという期待があります。楽しみですね。
それにかこつけて、現代の評論家を取り巻く諸問題について書こうと思います。
評論家がなぜ評論をするかについては大きく以下の3パターンがあるのではないかと思います。
①研究として評論する
②仕事として評論する
③自己実現の手段として評論する
①は研究論文を書くようなことです。作品自体とそれを取り巻く社会との関係に着目し、作品そのものを分析的に捉えていくような評論です。つまり、作品というパズルのピースがあったときに、その形がどのようなものであるかを明らかにすることだと思います。そのためには、補助線を引いて形を抽象化してみたり、他の作品と比較することでその形の特異さを見出したり、そのパズルのピースがハマる周辺がどのような形をしているかを明らかにしていくことだと思います。そのような領域において、評論家の存在は黒子的になると思います。誰が評論しているかではなく、何をどのように評論をしているかということの方が重要だと考えられるからです。
なぜならば、属人性を排除した上でも成り立つようなものこそが普遍的な分析であると考えられるからです。
②は例えば雑誌やWebに掲載される書評などが該当するものです。そこには、その評論によって何らかの価値を生み出す意図が存在し、しばしばその対価が発生しています。そこで生み出される価値とは、例えば、ガイドブック的であったり、宣伝的であるもので、作品の楽しみ方やその作品が持つ価値を多くの人に広く紹介するようなものです。このような仕事としての評論により、前提知識や受け取り方の分からない人にそれを上手く受け取るための道を示すことができたり、存在が知られていない作品に向けて人を導く導線を生み出したりすることができます。
そこでの評論は、何らかの心地よい物語として存在することが多いと思います。その評論の読者は、その物語に身を任せることによってスムーズに価値を受け取ることができるようになります。
③は評論をすることが、評論家自身の利益になるようなものです。つまり、その評論をしている評論家自身の価値を高めようとしているということです。たとえば、この分野において自分は詳しくて理解力の高い人間だよね?とか受け取る感性の優れた人間だよね?という評論家自身の自己アピールの性質が強い評論です。
このタイプの評論は、場合によってはそれを読む人にとって価値を感じにくいものになったりします。なぜならば、評論の目的が作品ではなく評論家のためのものであるため、その評論を読んだところで感じられるものが、評論家からの「私ってすごい人間だよね?」というメッセージしか読みとれなかったりすることがあるからです。
作品の話をしていると思ったら、知らん評論家の自慢話を読まされたと感じたときに、その読者は期待に応えて貰えなかったためにその評論に対して怒りを覚えるかもしれません。
この手のタイプの評論があるべきではないというわけではありません。人が自分の利益になることをすることは悪いことではないからです。しかしながら、そこで書かれた評論は、その読者からすると価値を感じにくいものになりがちだと思います。
ある評論があったときに、それが①②③のどれかに分類されるかというと、それは明確ではなく、ある程度それぞれが混ざったものになることも多いのではないかと思います。雑誌に書評として頼まれた内容でありながらも、学術研究のような文責を含む評論もあるでしょうし、学術論文のような体裁の中でも、中身から評論家の自己アピール要素を除外しきれないようなものもあるように思います。
僕が3つの分類を提示したのは、一口に評論と言ったとしても、どのようなものを評論と言っているのかによって話がすれ違ってしまう可能性が高いと考えているからです。評論とはなんたるかを話す上でも、その中のどういう部分がどういう種類の評論として書かれているかという部分を捉えながらでなければ、「自己アピール文でしかないこと」を批判しているのに、「学術的な批判の存在を否定するのか」と反論されたり、「作品が何たるか」を分析的に論じているのに、「お金をもらってやっている書評で批判的なことを言うとは何事か」と批判されたりと、そもそも何について話しているかがすれ違う不毛なやり取りが発生してしまったりします。
さて、②は商業的な要請によって存在しており、③は個人の自己実現の話でしかないため、評論一般の価値について語られるときは、①について離されていることが多いのではないかと思います。しかしながら一方で、世の中には①のような作品そのものについて研究的に語られる評論が存在できる場所は少ないのではないかと思います。
なぜならば、①のような評論を行うことによって食っていけるだけのお金を稼ぐことができる人はまれだと思うからです。そのような文章を読むためにお金を払おうと思う人は少ないでしょうし、研究者としてアカデミックな資金を獲得して行える人もいるかもしれませんが、そう多くはないでしょう。
であるならば、他に食い扶持のある評論家が採算度外視で自分の持ち出しで書く必要が出てきます。その結果、数が出てきにくいのではないでしょうか?
それによって、多くの人が目にしがちな評論は②か③の割合が多くなってしまうのではないかと考えています。つまり、②に関しては「どうせ仕事で書いてるんだろう?」という否定的な目線、③に関しては「それはアナタの自己アピールでしかないだろう」という否定的な目線が注がれやすく、評論家という存在に対しての尊敬が生まれにくいように思います。
このようなすれ違いが、「評論家の銅像は立たない」というような言葉の下地にあるように思えていて、評論には確かに価値があるはずなのに、それが特に現代では、上手く認められていないようなことがあるのではないかと感じています。
この傾向は、インターネットの普及以後の誰しもが、見るものであり見られるものであるという双方向性から逃れられなくなってから加速しているように思います。情報を一方的に発信できるのであれば、評論家はある種の権威で自分に塗り固めても、それを剥がされにくかったと思いますが、今では評論そのものも評論に晒されやすく、そこにも①のような評論だけでなく②や③も入り混じることで、様相は混沌となってしまいがちです。
なので、そのような環境の中では、ファンやアンチの戦いのような評論ばかりが目立つようになり、純粋に作品のみに向き合った評論は成り立ちにくいように僕は感じています。
しかしながら、僕が色んな人と話す中ではそのような評論に出会うことがあります。それも頻繁にあります。僕は漫画家として活動しているので、別の漫画家さんや編集者さんと話す機会も多くあるのですが、彼らの口から、純粋な作品分析としての評論は頻繁に語られており、そこには自分にはなかった視点や自分にはなかった価値判断があったりして、聞いていてとても面白いと感じています。
つまりこれがどういうことかというと、作品分析や社会における作品の在り方を語るような評論は、それ単体では生活の糧になるようなものにはなりにくいですが、それらの評論を踏まえた上で、自分独自の作品作りを行うことで、評論能力でお金を稼ぐことができるように実はなっているということだと思います。
それは、評論家が評論家として純粋でいようとした結果、実務家になってしまったという不思議な話です。
ここで「らーめん再遊記」に戻ってきますが、本作での芹沢さんはまさにそれに近しい立場として、活動をしているのではないかと思います。セミリタイアしたことによって、色んなところに顔を出しては、評論もするしラーメンも作るというその両方をやっており、評論能力と実務能力が互いに補い合っているように見えるからです。
「らーめん再遊記」における現在の話は、評論家を目の敵にするような実務家と、実務家の思い上がりと欠けた視点を問題視する評論家の戦いが描かれようとしています。その過程で既に、実務家の評論領域における問題点や、現代の評論のあり方の問題点も出てきています。
なので、このエピソードの中で、評論とは何かということがくっきりと浮き上がっていくような内容が読めるのではないかと期待しており、今後の展開をとても楽しみにしています。