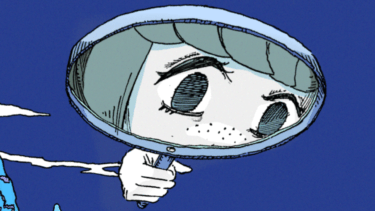どうもこんにちはえのきです。
割と友人の話す時の言い回しで「時計じかけのオレンジスタイルで見せよう」「時計じかけのオレンジで頼む」みたいなことを言います。


作中であったルドヴィコ療法のシーンのことですね。作中で治療、と称して強制的に映像を見せられるシーンで身内で会話している時に「コンテンツのインプットはしたいんだけど日々の疲れから怠惰に流されてしまうのでおすすめを強制的に見せてくれ」みたいなニュアンスでこれを引用しているわけです。
そんな話をしていた時が人生で定期的に訪れるジョジョを読み返していてやたらとジョジョについて考えるタイミングだったもので、不意に自分の中で「これどういうことなんだろうな〜」と長年考えていたポイントにしっくりくる見方が出来たので今回はそれについて書いてみようかと。
不意にしっくりきたこと、それはジョジョ三部で敵キャラであるンドゥールの語った『悪の救世主論』です。
悪の救世主論とは、そしてその疑問点について


悪の救世主論とは(正直まあ『論』と言えるほどのものではないのですが)ジョジョ第三部の作中後半戦で登場した強敵である盲目の男であるンドゥールが決着の際に語った言葉です。
『死ぬのはこわくない
しかし
あの人に見捨てられ
殺されるのだけはいやだ』
悪には悪の救世主が必要なんだよフフフフ
ラスボスであるDIOの単なる敵役としてではない底知れない魔的な魅力を象徴するセリフです。
自分はジョジョ五部が連載されていた時期が小学生で、後からジョジョを知って今ではイマイチ理解を得られないかもしれませんが『絵がキモいから読みたくない』と周りが誰も読んでくれない中「いやこの漫画は面白いだろ、真剣に読めよ!クズカス共がッ!!!」と一人で憤りながらコミックスで遡って読んでいたのですが、そんな時に読んだンドュールのこのセリフ、すごくインパクトのある言葉でした。
『救世主』という漠然とした『善』のイメージの言葉と『悪』という言葉がくっついているこの違和感。一部の時とは違い、DIOの顔は対面する時まで明かされず、異様なカリスマ性が演出され続ける第三部。
その中で強敵でありインパクトを残したキャラクターであるンドュールのこのセリフ。
「悪の救世主って、何なんだ??」
というのは強烈な引っ掛かりがありました。
当時はそのまま読み進め、DIOの圧倒的な存在感とそのスタンド能力、シンプルかつ圧倒的に強い『時を止める』という特異性で「なるほど、こういうことか」と思っていました。
ただ、その後人の感想を読んだり、自分も時間が経ってから読み返してみたりして、そこについてやはり疑問が湧いてきました。
「ンドゥール、付いていく人、間違えてない!?(まぁ人ではないが)」
という疑問です。
DIO、結構読者の間で語られている気がするのですがそのカリスマ性の演出に対して、よくよく読んでくると一部の時から変わらない小者、ゲス野郎的な性質は変わらず残っていて、余裕がなくなるとそれが平然と出てくるのですよね。
承太郎とのラストバトルも段々と顔がカリスマ性を纏っていた作画から歪さを感じる顔つきに変わっていたりと、そんなDIOの悪性は結構自覚的に描かれていたと思うのですがその悪あがきっぷりが潔さとは真反対なんですよね。
卑怯で狡くて、往生際が悪い。
カリスマ的演出のマジックが解けて読み返してみると「こいつ強いけど本当どうしようもねーな!」感がDIOは出てくるわけです。
そうなってくると自然とンドゥールの『悪の救世主』論がわからなくなってくるわけです。
「なんでそうまでしてDIOに心酔したわけ?」となってくる。
結構な間、自分は「まぁリアルタイム連載でのブレなのかな」と思考を止めてしまっていました。
ただ、ジョジョについては色々人生のタイミングで読み返して、再考を重ねていたわけです。
それで冒頭書いた『時計じかけのオレンジ』の話をしていた時に戻ってきます。
映画『時計じかけのオレンジ』で感じられるカタルシス、それはンドゥールの語る『悪の救世主』論と共通するものがあると感じたからです
映画『時計じかけのオレンジ』のカタルシス、誰もが持つ悪性の肯定
『時計じかけのオレンジ』、初めて見始めた時の印象は「怖い」でした。
とにかくアレックスが怖い。あまりにも『悪』すぎる。
暴力を容赦なく、そして楽しそうに振るう様があまりにもストレートすぎてシンプルに自分がその暴力を振るわれているような恐怖が湧いてくる。
アクション映画的な爽快感のある暴力というよりも恐怖が先に来たんですよね。
ですがそれは見続けているうちに不思議と印象が変わっていきます。
アレックスのクラシック趣味という『悪』と不一致であるようでいながら混ざり合っている性質。突き抜けた悪であるが故のどこか爽快さを感じる気持ち。
そうして作中のルドヴィコ療法のシーンの何とも言えない嫌さ。そしてその後のアレックスの哀れさ。
初めは恐怖を持って鑑賞していた存在であるアレックスに不思議とのめり込んで見てしまっているんですよね。これがこの映画が名作と呼ばれる由縁なのだなと。
そしてラスト、失った、奪われたはずの『悪』を取り戻したアレックスを見た時の異常ともいえる高揚感。
多分この映画が好きな人は結構な割合でこのカタルシスは共感してもらえるんじゃないかと思います。
これについて思ったのは自らの内側の悪性、を肯定された気がする心理があるんじゃないかと思うんです。
作中のアレックスの振るう『悪』は確かに凶悪です。並々ならぬものがあります。普通の人ではいきつかない領域に行ってしまっている。
だけど、同時に人には大なり小なり加虐性がセットされていると思うのですよね。
それは日常的な運動や趣味で解消できる人もいれば、職場などのパワーハラスメントや、街中でのトラブル、さまざまな形で発散したり、表出したりしているわけです。
もちろん、そこをしっかりと理性でコントロールしている人の方が多いと思います。
でも、そこにはきっと制御している『悪』がある。
アレックスが『悪』を奪われた時の悲しさはそこにあるような気がします。
確かに遠い存在の凶悪であったアレックス。でも作中を通じて『アレックス』という存在を知ることで徐々に卑近な存在になっていきます。
そこで『悪』が剥奪されること。
それは映画を鑑賞している自分自身が同じ状況になったら……。
同じように『悪』を奪われたら……。
という、恐怖があるのではないかと思います。自らの持つ、切り離すことが難しい要素が罰せられたら……という恐怖。
そこが取り戻されることで、凶悪であり、歪であるにもかかわらず『自然』を感じる存在にアレックスが返り咲く。
そこが強烈なカタルシスの要因である気がするのです。
では、DIOの持つ『悪の救世主』性とは?
誰もが持つ弱さ、その歪な肯定
ジョジョの作者である荒木先生はこのようなコメントをしたことがあります。
(前略)「悪い事をする敵」というものは「心に弱さ」を持った人であり、真に怖いのは弱さを攻撃に変えた者なのだ。
コミックス版ジョジョ46巻著者コメント欄
この『悪』論、個人的に今なお非常に納得がいく言葉です。
大人になって、世の中で起きた事件の背景に想いを馳せることがあります。続報や、様々なニュースをみることがあります。あらゆる愚かさの詰まった事件もあります。
それでも、その背景に目を向けた時、許せない事件であってもその中にifの自分を見てしまう時があります。
「この人の悪、は自分も持っているかもしれない」という視点です。
荒木先生はその観点をジャンプで週刊連載をしていた時から持っていたのではないかと思います。
四部は特に顕著ですが、それは初期からその芽を感じることができます。一部からのディオや、二部のストレイツォ。様々な『弱さを攻撃に変えてしまった者』が思い浮かびます。
だけど、それは子供の時よりもずっと実感のある存在となっています。
人は常に強く、正しくあれるわけではない。
弱り、迷い、葛藤する。そんな存在が人間であると感じます。
そして道を違えてしまった人々がいる。もう、元の道には戻れないところまで行ってしまった、それでもなお生きる時間が尽きなかった人がいるのだと思います。
そんな時に三部のDIOが現れたらどう見えるのでしょう?
悪という自らの弱さを無限に肯定し、そしてそのまま世界を牛耳ろうと悪を行使する圧倒的な強さを持った存在。生半可な攻撃では死なない不死性、そして目的のためなら手段を選ばない精神性。
それはンドゥールの語る『悪の救世主』と違わぬものではないでしょうか。
人のもつ歪な悪性、その奇妙な肯定にこそ、DIOの悪の救世主性は存在するのではないでしょうか。
本筋とは少しずれますがDIOの『肉の芽』もそのような概念を形にしたメタファーなのかもしれません。悪を肯定し続ける、その代わり悪から離れようとした存在を罰するという歪な救いの象徴。これについてどこかで書いてみても面白いかも知れませんね。
それでは今回はこの辺で。思ってもみない繋がり方をするかもしれないので、好きな映画と好きな漫画などを繋げて考えてみるのはどうでしょう?結構楽しいですよ。
それではまた!