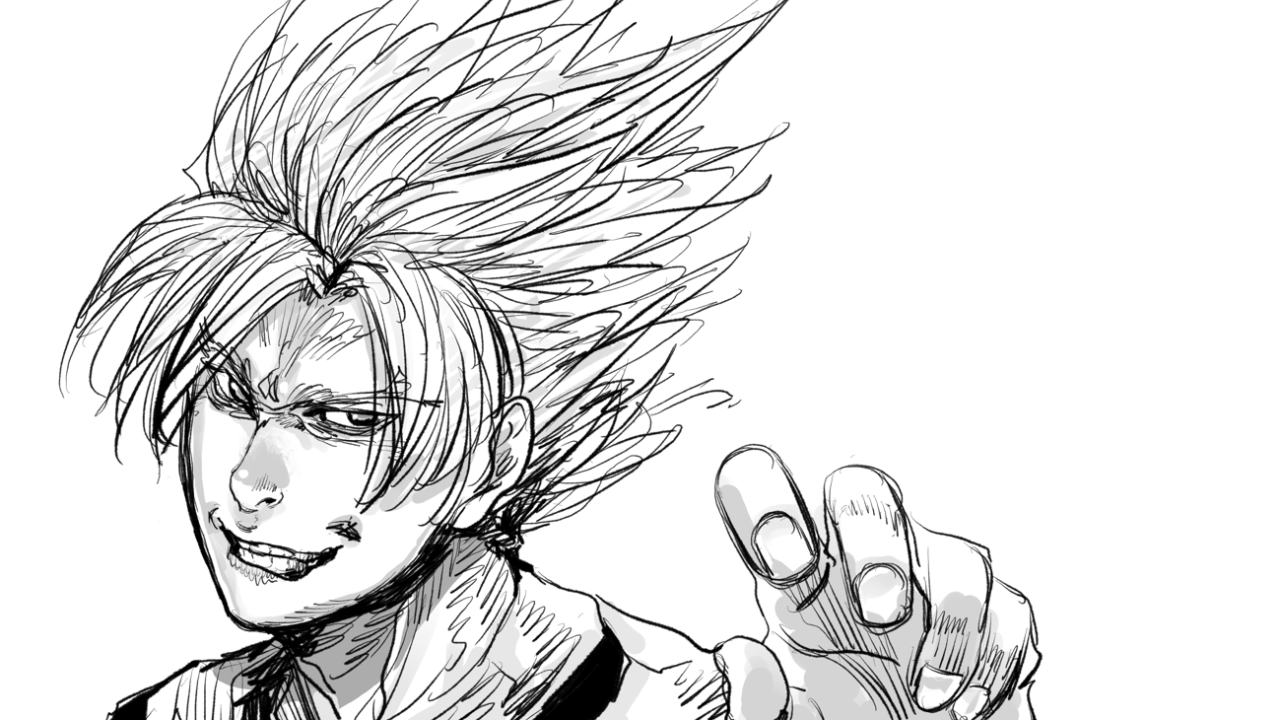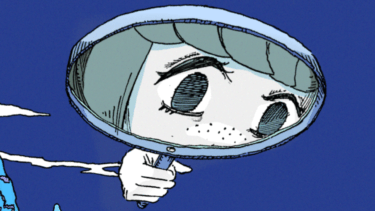昨年、鳥山明先生が亡くなり、現在放映中のアニメ、ドラゴンボールDAIMAが鳥山明先生の手の入った最後の作品となるのかという寂しさとともに、これまで読んできた作品から沢山のものを得てきたことについても思いを馳せる1年になりました。


鳥山明先生の漫画のどこがすごいのかについて、絵に比べると比較的語られることの少ない、ストーリーと観点とキャラクター構築の観点の2点から、僕がドラゴンボールに関して感じている非凡さについて書いてみようとおもいます。
1 ストーリー観点:大胆な省略による密度の高い物語展開
ジャンプ漫画におけるドラゴンボールの特徴のひとつとして、ストーリー漫画であるにもかかわらず、ページ数が短いという点があります。ジャンプ漫画は基本19ページで描かれていると思いますが、ドラゴンボールは基本的に14ページ(そのうち1ページは扉)だったと思います。
これはおそらく前作のDr.スランプがギャグマンガで14ページであったことを踏襲しており、ドラゴンボールも初期はコメディ色が強い漫画であったため、あるいはこのページ数に慣れていたため、このような形式になったのではないかと思います(へたっぴマンガ研究所にもギャグマンガは14ページだと書いてありました)。
ページ数が少ないということは、それだけ1話で描けることが少ないということです。しかしながら、ドラゴンボールの1話には物足りなさを感じることはありません(少なくとも僕はそうでした)。なぜそうなるかというと、14ページの中にちゃんと読み応えのある展開が描かれているからだと思います
14ページを上手く使うには、全体のページ数の中で読み応えのある部分にページを割く必要がありますが、それは逆に言えば「描く必要のない部分を大胆に省略する」必要があるということです。なぜなら、冗長な場面を描いているとページが足りなくなるからです。
そうやって。描く必要のないことを省略できれば、描くべきことのみに注力することができ、読者が面白さを感じられるページが増えることになります。そこに結果的にドラゴンボールという物語のテンションの高さを維持する効果があったのではないかと僕は考えています。
鳥山明先生はよくインタビューで「面倒くさかったから省略した」というようなことを語っており、それは本音でもあると思うのですが、ならばどう省略するか?という部分に非凡な手段が使われていると感じています。
例えば、「説明的な描写」はテクニックや力技で回避をしています。よくやる手法としては、新しいキャラクターが登場するときには2人組で登場し、2人の会話の中に情報を混ぜ込む形で、キャラクターの紹介と状況説明を同時にやるテクニックを用います。また、僕が力技と言っているのは、例えばナメック星に到着したばかりの悟空が状況把握のためにクリリンの頭の上に手を置くだけですべてを読み取って把握する描写などです。
この記憶読み取り能力をその後は使うことはありませんが(病気で寝ている間にすべてを把握するなどの類似するものはある)、「読者にとっては自明」だが「到着したばかりの悟空は知らない事実」を説明することにコマを割くことは。内容の辻褄合わせでしかなく面白さがありません。なので、一度しか使わない特殊能力を使ってでも大胆に省略するという技があります。この大胆さを真似できる漫画家はそうはいません。
中でも物語展開上のすごい発明は、人造人間編において「悟空が瞬間移動の能力を覚えること」です。これは明らかにその後の作劇の効率化のために登場していると思います。
瞬間移動の登場によって、移動時間を完全にゼロにすることができるようになりました。例えば、悟空がセルと話をするためだけに瞬間移動で会いにいく場面がありますが、瞬間移動があることで場所移動のコマを省略することができるようになります。これによっていつでもコマ消費を最小限に場面転換をできるようになり、お話を進める上での無駄なコマを大きく削減することができるようになっています。
ドラゴンボールにはこのような「目的に対して、過程を経ずに、たった1手でそれを実現する存在」が多く出てきます。例えば修行時間が必要なときには、1日が1年に相当する精神と時の部屋がいきなり登場します。ホイポイカプセルなどもそうですし、そもそも、なんでも願いを叶えてくれるドラゴンボールの存在がそうです。
ここには何らかの不思議な効果を1手で実現する発明が登場していたDr.スランプを描いていたことが生きているように思えます。目的があり、それを実現する必要があるのであれば、段取りなど踏まずにいきなり実現してしまえばいいという率直さです。
この工夫よって、他の漫画であれば何倍もページを割かなければできない展開を、短いページで描き切りやすくなりました。
このように、必要と不必要を見極めて、不必要な部分を大胆に省略することにより、面白い部分だけを表現し続けたのが、ドラゴンボールの作劇のすごいところだと思います。
2 キャラクター観点:悟空というキャラクターの持つ葛藤
ドラゴンボールの主人公である悟空というキャラクターの特徴を一言で表現するなら、「こいつがいたらなんとかしてくれる感」であると思います。これは、未来のトランクスの世界のブルマがトランクスに対して言っていた話であり、鳥山明先生もそこに自覚的であったことがその描写から伺えます。
未来のトランクスの世界は、読み切りや、アニメスペシャルでも描かれましたが、とても希望のない世界です。それは悟空の不在によってもたらされた雰囲気であり、その希望のなさから逆に「悟空さえいれば楽観的になれるのに」という気持ちがあることを思い起こさせてくれるものでした。
だからこそ、未来のトランクスは悟空を病気で死なせないためにタイムマシンで過去にやってくるわけですが。
悟空の「こいつがいればなんとかしてくれる感」は、逆を言えば悟空が来てくれるとなんとかしてくれてしまうために、「悟空の到着をいかに遅らせるか」という作劇に繋がっていきます。ベジータとナッパに対してあの世から戻ってくる時間、ナメック星への到着の遅れ、精神と時の部屋に入っている時間など、悟空のいない時間にピンチは起こり、読者も悟空を待望し、悟空の到着で期待に応えてなんとかしてもらえるという気持ちのよいサイクルが繋がっていきます(これは「神と神」ではセルフパロディとして、必要なタイミングまで登場をあえて待っていたというギャグにも繋がる)。
人造人間編は、「悟空がいればなんとかしてくれる」ということ自体が終盤のテーマとなっていると感じています。悟空は、自分のいない未来のことを知ってしまったせいで、「自分がいなくても、次の世代だけで何かがあっても解決できるようになってほしい」と考えるようになったように見て取れるからです。
完全体のセルと戦うときに悟空がさっさと降参を宣言して、悟飯に戦いの座を譲ろうとするのはそのためだと思います。セルに仙豆を渡してわざわざ解決させたのも、悟飯の力だけで完全体のセルを倒せるという事実が欲しかったのではないかと解釈できます。
自分がいなくても次の世代が立派にやれると思ったからこそ、悟飯に期待したのだと思うのですが、悲しいかな悟空の判断は間違っていて、悟飯は悟空とは違う人間ですし、座を譲っただけでは悟空のように振る舞うことができませんでした。
結果として、その責任をとるように悟空は自らの命を犠牲にすることになります。悟飯も見事セルを倒してのけ、それによって今度こそ、その場所を悟飯に譲って終わったかのように見えたのですが(魔人ブウ編に続く)。
魔人ブウ編とは、悟空をドラゴンボールの物語から解放するためのお話であるように思いました。一度主役の座を降りた悟空が再び呼び戻されるお話の中で、悟空は「自分は主役から降りるべきだ」と捉えており、その証拠に、超サイヤ人3になったときに魔人ブウを実は倒せたはずなのに、今の世代が倒すべきだからと遠慮し、悟天とトランクスに嫌われながらも今の世代に託そうとしました。
しかしながら、彼らもピッコロも、パワーアップした悟飯もブウに吸収されてしまい、戦いの最後の最後ではライバルであったベジータすら悟空に全てを託そうとします。それは感動的な場面でありながらも、最後は自分だけになるという悟空の孤独の話としても解釈できます。
ただ、その最後で魔人ブウを倒す決め手になったのが、ミスターサタンが声をかけて力を貸した「悟空のことを知らない人たちの力」であったことこそが。実はこのお話の救いであったと思いました。それは「悟空がいなくてもこの世界は大丈夫」だと思わせる力であったように思うからです。
たったひとりで戦い続けた魔人ブウを、最後に悟空が労ったのはそういう意味もあったのかもしれません。みんなの期待を一手に背負って一人で戦うことになっていた悟空と、一人で戦い続けた魔人ブウは、合わせ鏡のような存在だとも解釈できるからです。
そんな魔人ブウの生まれ変わりであるウーブを鍛えようとするところで物語が終わるのは美しいなと思いました。それは、悟空はついにみんなの期待を背負って一人で戦う存在から解放された物語であると思ったからです。
悟空自体はあっけらかんと物事を語るため、一部の読者からサイコパスなどと揶揄されることもありますが、一人の少年が成長し、多くの人々からの期待を一身に背負った存在となって、そして、そこから解放されていくという神話的な物語として完成されているなと思いました。
まあ、その後、またアニメで続編は始まり、物語に連れ戻されるのですが。でも、超ヒーローでは、ついに最後まで悟空がやってこない物語が描かれたのがよかったですね(悟空がいない時期を舞台にしたアニメオリジナル話はありましたが)。
まとめ
さて、上記2点がドラゴンボールの他の漫画と異なる特徴的なところだと僕は考えています。
まとめると、短いページで面白い場面を描くために、面白いところ以外をあまりにも大胆に省略することが徹底されていたのは、他の漫画ではなかなかできていないところではないかと思います。また、ドラゴンボールの連載をやめたかったという苦悩が物語の中に反映されているのか、「悟空を主人公の責務から解放しようとする物語上の流れ」と「にもかかわらず魅力的過ぎて何度でもよみがえって来てしまう」というせめぎ合いが葛藤のうねりとなって、結果的に特異な物語展開とその深みを生み出していたと思いました。
用意されていた予定調和ではなく、悟空の物語を終わらせるという強い力が、終わらせない抵抗を最後寄り切った感じがしていて、その部分が今読み返してもなお面白いと思います。
やめたいのにやめられず、にもかかわらず手を抜いて投げ出すことはしないという生真面目さの生み出した奇跡のような物語ではないかと感じられたからです。
鳥山明先生が亡くなった後も、ドラゴンボールは続いていくのだと思います。また、ドラゴンボール自体だけでなく、鳥山明先生に影響を受けた無数の人たちが、新しい漫画などを生み出していくのだと思います。
でも、そのオリジンである鳥山明先生ほどに、大胆なことを徹底してやることはなかなかできないものではないかと僕は考えており、だからこそ、今なおオンリーワンの漫画家であるように感じています。