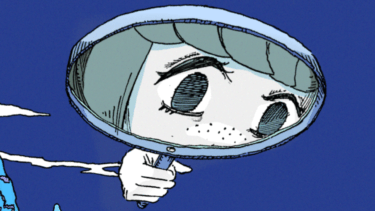「バクマン。」は二人のコンビで漫画家になる漫画家漫画ですが、その序盤に、「人気漫画の共通点は刀」という発見の話があります。本作は週刊少年ジャンプで連載され、彼らはジャンプでの連載を目指す立場なので、ジャンプ漫画を実例に挙げて刀が出てくるという話をします。
ただし、その基準はあいまいで、主人公でもない刀を使うキャラが出てくるだけで条件成立という感じになっているので、がばがば過ぎると思って連載当時は半笑いで読んでいたと思います。
しかしながらその後、まさに刀を使う「鬼滅の刃」が国民的な漫画となり、大ヒットした「呪術廻戦」にも多くの刀使いが登場しますし、今人気上昇中の「カグラバチ」は刀を主軸に置いた漫画です。
その結果、人気漫画には刀が出てくるのではないか…と段々と思うようになってしまいました。
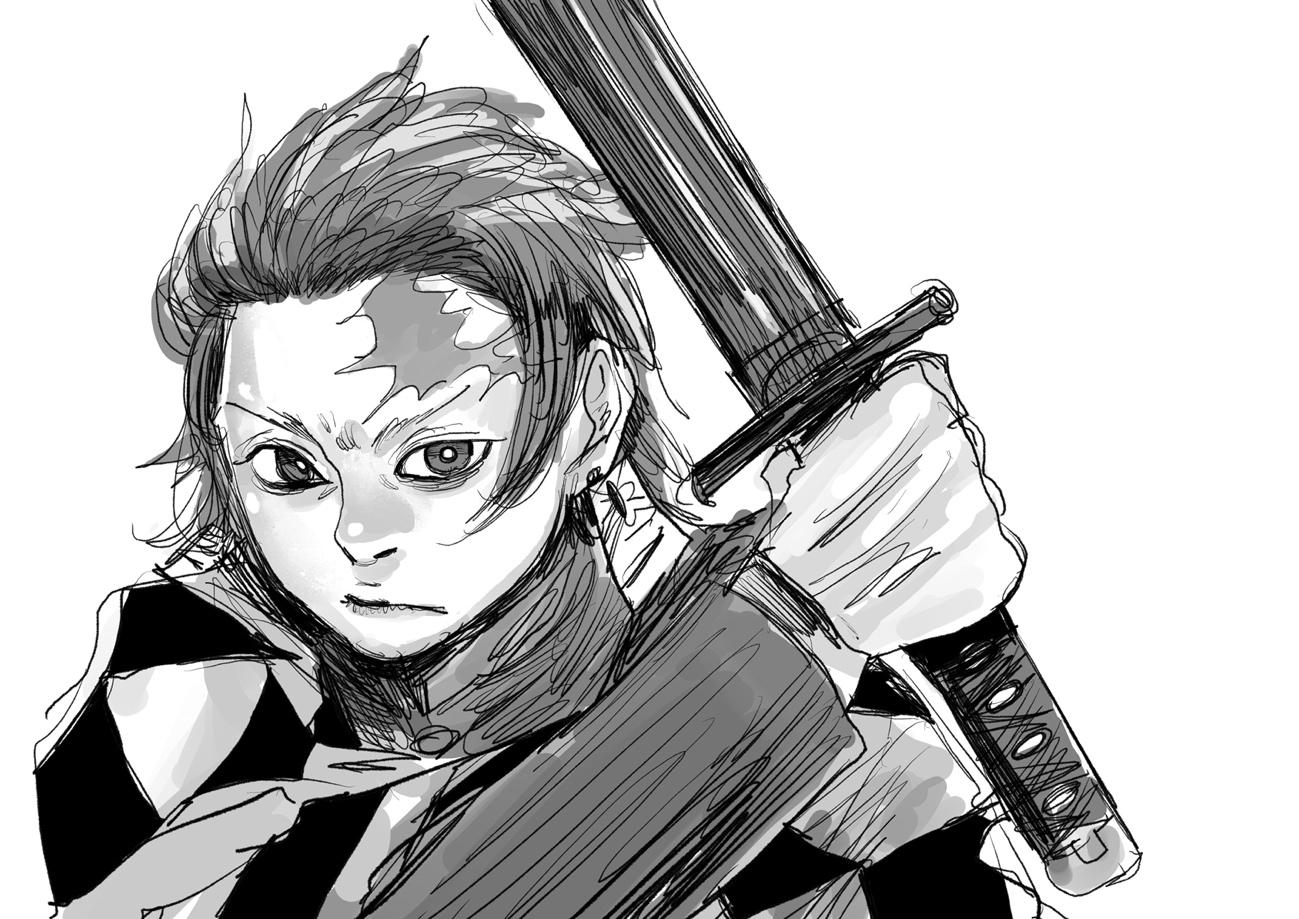
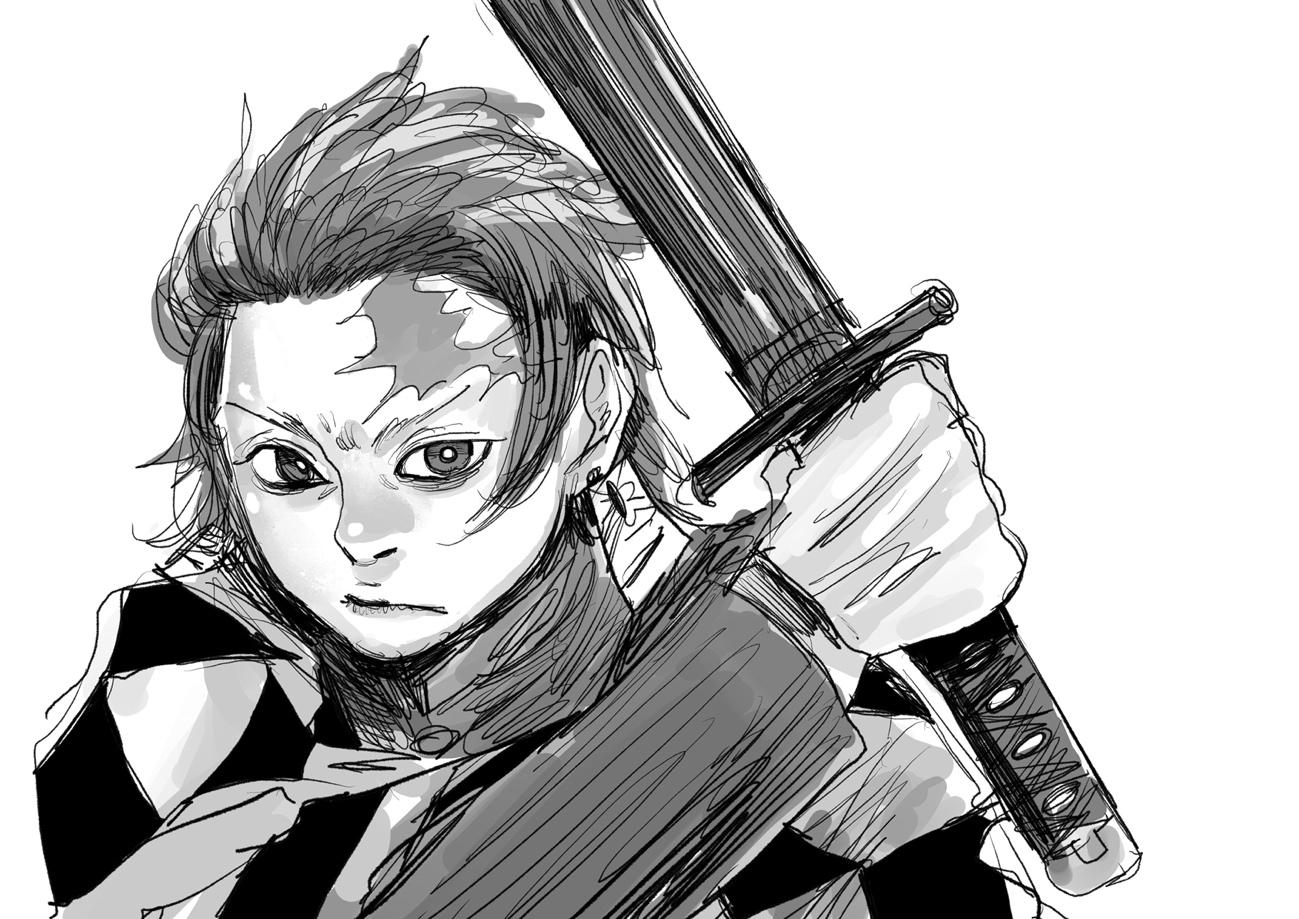
ここで重要なのは、刀が出てくる漫画が全部人気になっているわけではなく、人気漫画には刀が出てきがちという話だと思います。
そこについて2つの観点から考えてみたいと思います。
①刀が出てくる漫画と出てこない漫画の作劇上の違い
刀が出てくる漫画と出てこない漫画は何が違うのでしょうか?それは「刀で斬る」という出来事が漫画の中に登場するということだと思います。つまり人が殺し合うような描写があるということです。
つまり、「人気がある漫画には刀が出てくる」というのは「生死に関わるバトル漫画は人気がある」ということと近いなと思います。しかし、バトル漫画の中でも刀が出てくる漫画と出てこない漫画があります。
素手の格闘技で戦うバトル漫画と比較した刀で戦うバトル漫画の特徴は、「一撃で致命傷になる」ことではないかと思います。つまり、ページをめくった瞬間にズバッと斬ることで生死に関わる決着がついているような展開を、刀のバトルであれば描きやすくなります。ただし、素手で一撃で他人を死に至らしめるような描写も可能ではありますが。
では、次は銃火器が登場するバトル漫画と刀漫画の違いを考えてみましょう。銃火器でも一瞬で決着はつきます。しかしながら、一瞬で決着をつけや過ぎるということが難しさでもあると思います。つまり、刀の戦いであれば、つばぜり合いのような攻防の積み重ねも描けますが、銃火器を使った場合、当たらないか、当たれば一撃で決着がつくものになりやすいということです。
つまり、生死に関わらず攻防を描く⇒生死に関わる決着を描くという軸があったとき、刀は素手と銃火器の間に位置するという理解になります。つまり、「攻防」と「一瞬の決着」のどちらも描ける可能性があり、刀の登場するバトル漫画は上手く描けばその両方を描けていいとこどりができるのではないかと考えました。
この辺りを考えてみると、刃牙シリーズにおける刃牙道のことが思い当たります。刃牙道は、宮本武蔵が現代に蘇るお話で、宮本武蔵は刀を使います。それまで素手での格闘を中心的に描いてきたシリーズ(いや死刑囚編等には様々な武器や道具を使う描写もありましたが)における刀の登場が、それまでとバランスを崩す様子がそこに見て取れるのではないかと思います。
具体的には、烈海王が宮本武蔵との戦いの中で死にました。刀で斬られたからです。刀で斬られたら普通は死にます。これまでどれだけ殴られても、身体が爆ぜても、噛みつかれたとしても、なかなか人が死ぬことがなかった本作において、とても印象深いお話でした。刀で両断されると人は死にます。
ちなみにこの宮本武蔵は銃を見て、「道にはならん」と表現しました。
刀が登場することで、作中に攻防が存在しながらも「死」が登場しやすくなり、一撃で死に至らしめるという刀は漫画演出上に効果的に使うことができるアイテムであると言えると思います。
一方で、刀の取り扱いが難しいのは、逆説的ですが「死んでしまう」ということでしょう。
前述の刃牙道のように、刀で斬られると人は死にがちですし、死ななくても斬られた部分の人体には欠損が生じたりします。「シグルイ」などでは、その欠損した部分を描くことでその暴力性と取り換えしのつかなさを描いたと思います。しかしそれはとてもストレスの高い描写だと思います。
そういえば漫画の展開でありがちだと思うのは、「指を斬られたキャラは死にやすい」というもので、なぜならそれで生き延びた場合、その後、足りない指の描写をし続けなければならないからだと思います。なので、その欠損を継続的に描くわけではない、つまり、そこで死んでしまうキャラで用いられがちな描写だなと思ったりします。
そのように作者にとっても読者にとっても刀があることで欠損が生じる描写はできれば避けたいもので、その代わりに、再生や治療ができる特殊能力の存在(「鬼滅の刃」の鬼や、「呪術廻戦」の反転術式)や、斬られて死にはするが後で生き返る展開(「魁!男塾」など)とセットにすることで描写をマイルドにするような別の工夫があることが多いのではないでしょうか?
「ドラゴンボール」では、悟飯やヤジロベーが刀で斬るのは恐竜やサイヤ人の尻尾というストレスが少ない部分ですし、ばらばらに斬られたフリーザはそのまま死にます(後の映画で生き返ります)。刀を効果的に使う場合には、それ以外の配慮が存在していることを感じます。
このように考えていくと、「るろうに剣心」で主人公が逆刃刀を使っていることに意味を見ることができると思います。つまり、刀を使った作劇をやりながらも、「一撃で殺せる」という機能をオミットできることで、刀バトルにおけるストレスを削減することが構造的にできるからです。さらには、それを使うことが剣心という人間を構成する重要な要素でもあるので、複数の問題を同時に解決しており、アイデアだなと思いました。
まとめると作劇上、刀が登場するメリットは以下です。
・人の生死が関わる戦いを描きやすい
・わずかコマで人を死に至らしめることができる(素手ではやりにくい)
・にもかかわらず、連続的な攻防も描きやすい(銃ではやりにくい)
一方で、刀の取り扱いが難しい理由も以下があります。
・人の生死に関わるので普通にやるとどんどん人が死んでいく
・斬られると人体が欠損していくので読者にストレスが生じる
これらは、回復できる仕組みを用意すること、斬れない仕組み(逆刃刀、鎧、気による防御)を用意すること、欠損するぐらいなら容赦なく殺してしまうことなどとの組み合わせを行う取り扱いの難しさがあり、このバランスをとらないといけない部分に「人気漫画に刀が登場するが、刀が登場すれば人気漫画になるわけではない」という秘密もあるのではないかと思います。
「鬼滅の刃」で言えば、刀を使う鬼殺隊の相手が再生能力の高い鬼であるということが、派手に斬れるという部分の下地にあると思います。一方で鬼殺隊の側はダメージが回復することなく残る(治癒にも時間がかかる)という対比のバランス感覚が素晴らしいものだなと思いました。
②刀が出てくる漫画の絵作り上の違い
以前、藤田和日郎先生がテレビで、絵作りにおける「空間支配力」という話をしていたと思います。これはつまり、手に何か持たせたり、長い髪や服をなびかせたりすると、コマの中に占めるキャラクターの割合が大きくなり、コマの中の空間をより多く支配できるという話であったと思います(おぼろげな記憶で書いているので不正確ならすみません)。
刀を持たせるということは、このような空間支配力を高めやすくなるという絵的な効果があると思います。武器を構える、武器を振り回すなど、武器を持たせれば絵作り上の選択肢が広がっていくため、カッコいい絵を描こうとしたときには、素手よりも武器を持たせた方がバリエーションを付けやすくなるというメリットがあると思います。
「ベルセルク」のガッツが、大剣「ドラゴンころし」を振り回す絵を思い浮かべてみてはどうでしょうか?これが素手であったならば、ダイナミックさが減じてしまうかもしれません。武器を持っていてよかったですね。
空間支配力を考えると「るろうに剣心」では、九つの軌跡で突進しながら斬る九頭龍閃が思い当たりますね。突進しながら刀が九倍になるので、とても空間を支配しやすくなる技です。
そういえば「ヒカルの碁」でも確か、佐為とヒカルが、囲碁の戦いのメタファーとして刀を使っていましたね。これも刀を使うとカッコよく描けるからではないかと思います。
ここで言いたいことはとても短くシンプルです。「刀を持たせると絵をカッコよくしやすい」ということです。刀を効果的に使ってカッコよい絵を描ければ人気が出るのかもしれません。
さて、上記2点をまとめると、なぜ人気漫画に刀が登場するのかを考えると、刀は「登場させることで漫画演出上の選択肢が増えやすくなる便利なアイテムだから」だと思います。しかしながら、その使い方のバランスも難しく、効果的に使うに演出力が必要になります。つまり、人気漫画では、取り扱いの難しい刀も上手く使える技量があるから人気漫画である、ということなのかもしれませんね。
みなさんも何故人気漫画に刀が出てきがちなのかを考えてみましょう。