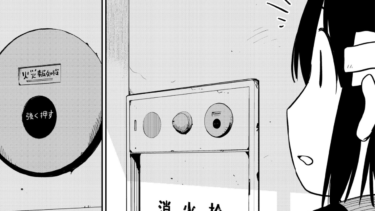呪術廻戦のスピンオフである呪術廻戦≡(モジュロ)の連載が始まり、死滅回游編のアニメの報せもあり、アニメと呪術廻戦ということで、呪術廻戦とエヴァンゲリオンとの比較の話をしたいと思います。
呪術廻戦のラスボスである両面宿儺には四つの目と四本の腕があります。これはエヴァンゲリオン第13号機になぞらえることができます。終盤の伏黒恵の肉体に受肉した宿儺には、宿儺と伏黒恵の二つの魂が入っており、これは第13号機に二つの操縦席が入るダブルエントリーシステムと同じと解釈することもできるからです。
伏黒の心はその底で助けたいものを助けられなかった絶望のままに沈んでおり、これは碇シンジです。それを助け出すのは、虎杖悠仁と釘崎野薔薇、宿儺の器として人の意図のもとに作り出された虎杖悠仁は綾波レイ、死んだかと思われたが眼帯をつけて復活した釘崎野薔薇は式波アスカラングレーです。
綾波ユウジと釘崎アスカラングレーが、伏黒シンジをスクナゲリオン第13号機から助け出すのは、エヴァンゲリオン新劇場版Qの最後からシンエヴァンゲリオン劇場版の序盤に重なりますね。


これは冗談です。真面目に書きます。
呪術廻戦とエヴァンゲリオンは根本のテーマ性に共通点があると思います。呪術廻戦における呪いとは人が生み出すもので、エヴァンゲリオンは自分と他人との関係の中での苦しみについて描いたアニメです。
エヴァンゲリオンにおける人類補完計画は、人間と人間を隔てる壁を取り払うことで、個人を消滅させ、全員が融合した一個の生命として人工進化するというものでした。主人公の碇シンジは、他人との関係の中で傷つきやすく、それゆえに人間関係にも積極的ではなく、誰かと接することで自分が傷つくことに常に怯えている少年でした。人類補完計画の発動は、そんな他人との間にある摩擦を消し去るもので、他人も自分もなくなれば傷つくことはなく心地よい世界がそこにあります。しかしながら、シンジくんは、たとえ傷ついたとしても他者のいる苦しい世界を選択します(旧劇場版)。
呪術廻戦における夏油傑は、呪いが存在する世界を、それを人間が生み出すことを憂いていました。人類が呪いを克服する手段は大きく二つ。「呪いを生み出す根本を断つ」か「全員を、呪いをコントロールできる呪術師にする」ことです。前者は人間が呪いを生み出す仕組みの解明で、技術的に目途も立っていない話です。しかし、後者にはもっと実現性が高い方法があります。それは、呪術師ではない人間を皆殺しにすることです。それができれば生き残った全員が呪術師になるため、目的は達成されます。
夏油傑による後者の計画は頓挫しますが、夏油傑の身体を乗っ取った羂索がその大枠を引き継ぎます。羂索は日本を覆う結界の要である天元を利用して、日本人の全てを超重複同化することによって、人間の持つ呪力を最適化するという強制進化を試みます。そこで行われることは、エヴァンゲリオンにおける人類補完計画と類似します。
人間と人間がいるからこそ、そこに呪いが生まれ、呪いは不幸を招きます。であるならば、人間を人間以外に同化させてしまうことで、この世界に廻る呪いの構造を壊すことができるのかもしれません。しかしながら、羂索の語る目的は夏油とは違っていて、1億人が超重複同化したときに生まれる何かが、その先にどん混沌を生み出すのかに興味があるというものでした。
僕は呪術廻戦を、人が存在するために、人間と人間の間に生まれる呪いと、そんな呪いの循環の中で翻弄される人々の姿を描いた漫画だと思って読んでいました。
エヴァンゲリオンでは、それでも他人がいる世界の中で生きることの選択と、その苦しさが描かれ(旧劇場版)、他人との折り合いをつけ、執着心を手放して送り出し、そして他人のいる世界で前向きに生きることが描かれました(新劇場版)。
では、類似する建て付けの中で、呪術廻戦で描かれたものは何でしょうか?僕はそれを「廻りを止めること」だと思いました。つまり、「同じように繰り返され続けるものを止め、新たな道に踏み出す」ということです。
人にとって絶望とは何でしょうか?僕は、絶望とは「今苦しみの中にいることは」とは違うのではないかと僕は思っています。なぜならば、その苦しみの先に希望が見えていれば、人は前に進めるからです。ならば、人間が絶望をするのは「何をしたところでどうせ結果は同じだ」と感じてしまうことだと思います。何をやったって同じなら、この先、何をやることに意義を見出すことができなくなります。ならば、繰り返される徒労の中で、人は疲れ果て、もうそこにうずくまることしかできなくなるでしょう。それが絶望です。
呪術廻戦において、繰り返されるものは、宿儺です。忌み子として生まれ、迫害され、呪いの力を持たない人間のままであればそのまま死んで終ったのに、特級呪物と化すことで他人の身体に受肉し、時代を超えて生を繰り返します。
宿儺は自身を「身の丈で生きている」と表現しました。彼が身の丈で生きているつもりだったのは事実でしょう。彼の存在の呪われたところは、「圧倒的に強かったこと」です。「誰も彼を負かすことができなかったこと」が宿儺の抱えていた呪いではないかと思います。なぜならば、負けることがなければ自分を改めるきっかけがないからです。自分の強さによって自分を正しいと証明できているように思い続けてしまうからです。
宿儺は「強すぎる」という呪いにかかっており、それゆえ変わることができず、終わらぬ生を繰り返しています。宿儺の呪いは敗北によって解けます。それは終わりなく勝ち続けてしまうという繰り返しの絶望から、敗北によってようやく解放されたという話ではないかと思いました。
この物語の大きな建て付けにも繰り返しがあります。それは、天元と六眼と星漿体です。天元は星漿体と呼ばれる人間を生贄として取り込むことで自分を変化させ、命を長らえ続けます。六眼の人間は、そんな星漿体を護衛する役回りです。このループを阻止しようとする試みは六眼が現れて阻止します。そのループを止めることに挑戦し続けたのが羂索です。彼は生まれたばかりの六眼の子供を殺したこともありましたが、それでも天元の同化の日に、星漿体と六眼は現れました。それは呪いの循環です。何度繰り返しても、六眼に守られた星漿体は、生贄として天元に捧げられ続けます。何をしたところで終わりがない絶望のループがそこにあります。
しかし、それが破られるタイミングが来ました。それは天与呪縛フィジカルギフテッドの男、伏黒甚爾によるものです。天与呪縛フィジカルギフテッドの人間は、生まれながらに呪力を全く持ちません。そのせいで因果の外に存在します。呪いの廻りは因果の廻りです。天与呪縛の男はその外からやってきて破壊をもたらしました。
そこで起こったことは悲劇でありつつ、終わらない呪いが解かれた話でもあったと思います。
しかしながら、天与呪縛フィジカルギフテッドの男、伏黒甚爾もまた呪力を持たないながらに呪われています。呪術師の名家である禪院家において、呪力を全く持たない伏黒甚爾は差別されて生きていました。彼は自分の息子、伏黒恵が禪院家に売られていくことを容認しますが、呪力を持つことを是とする禪院家の価値観の中で、呪力を持ち合わせているとはいえ、息子が生きていくことへの心配がありました。彼はイカレた男でしたが、自分の子供の幸せを願う愛情を持ち合わせていました。
その後、降霊術によって一時この世に顕現した伏黒甚爾は、息子の名前が禪院ではなく伏黒であることに安堵します。そして、自分が父親であることも告げぬまま、自分で命を絶ち、また死者に戻ります。それは、親の因果が子に引き継がれて繰り返される呪いへの危惧があったということで、その呪いが解けたことへの安堵の場面であったと思います。
釘崎野薔薇も同様です。彼女はエピローグにて、自分を捨てた母と再会します。母親は娘に母娘間の呪いのようなことを言いますが、釘崎野薔薇はその母の言葉に動揺せず、自分とは関係ない存在として扱うことができました。ここでも呪いは解けています。一方で、そこに祖母が現れたことで、母自身は逃げてきたはずの母娘の呪いに再び捕まる様子も描かれました。
虎杖悠仁は呪われた子供です。羂索の策謀によって作り出された、宿儺の器となるために生まれた子供です。その正体は、宿儺の双子だった人間の生まれ変わりのその孫、血筋も生まれも運命も呪われています。仕組まれた繰り返しの中に投じられた存在です。
そんな虎杖悠仁は、沢山の人の力を積み重ねた最後の槍の先端として、宿儺を倒します。それは廻る呪いに決着をつけた場面です。
そして、彼らの先生であった五条悟は、五条悟性を引き取って去っていきました。生まれた瞬間に呪術界が変わってしまったような圧倒的なスターの五条悟は、自分が死んでしまったあと、そこに必要なのは五条悟ではなく、また別の存在でいて欲しいと願っていました。その一人が虎杖悠仁であったということです。ここでも繰り返しが途切れることへの願いがありました。
羂索の過去は最後まで物語の中では描かれず、彼が何をきっかけに様々な策謀を巡らせることになったのかは語られません。しかし、彼が天元と星漿体の融合を阻止しようとし続けたこと、そして、芸人の高羽との戦いの中で満足を得ていったことからして、彼が憎んでいたのは「繰り返される予定調和」であったのではないかと思います。予定調和ではない混沌を望んでいるために、芸人のボケやギャグという、突飛なものに対する好意があったのではないでしょうか?
「どうせいつもと同じになる」という呪いへの絶望に、羂索は抗い続けたのではないかと思います。だからこそ、そうではない結末にたどり着くために、呪詛師でありながら、呪いという繰り返される予定調和を破壊することを諦めなかった男なのではないかと思いました。それは、肉体を乗り換えながら1000年という時の流れの中で、「どうせこうなる」という絶望に屈することがなかった希望の男であったとも見て取ることができます。
羂索の超重複同化は結局阻止されますが、彼は呪いの予定調和を破壊し、満足を得たので、ある意味勝った人間であったのかもしれません。
このように、呪術廻戦の物語からは、呪いの廻りを断つ構造が各所に見て取れます。永遠に繰り返す牢獄の中の絶望をいくつも断ち斬りました。しかし結局、世界から呪いは消えず、人は依然として争います。ただ、呪いの因果は存在し続けても、その中で閉じた円環ではなく、変化する螺旋を生きるような結末に至りました。
人間はこれからも他人の存在する中で互いを呪い、争いながら生きるが、でも同じことの繰り返しではなく、よりよく生きることもできるという希望の物語で会ったと思います。
もう少しメタな話をすれば、呪術廻戦はエヴァンゲリオンと似た土台の上に立ちながら、それとは少し変わった螺旋の結末を迎えます。その構造そのものが、呪いを解く物語として美しく収まったように思いました。
呪術廻戦には、エヴァンゲリオンだけではなく、他の色んな元ネタが存在します。数々の元ネタの繰り返しの中で、過去の作品を組み合わせただけの円環の中から抜けることはできないのか?という葛藤を元に、その先を描いたのが呪術廻戦という物語なのではないかと捉えることができます。
本作だけでなく、あらゆる創作は、過去の作品の影響下にあります。過去の無数の作品が既にある中で、それでも物作りをしていく意味を描いたという意味でも希望を描いたと言えるかもしれません。
呪術廻戦には、他にも様々な切り口の語り方があると思いますが、僕が他に書けるものとしては「呪術廻戦とエアマスター」というものがあります。しかし、それはまたいつか別の機会に。