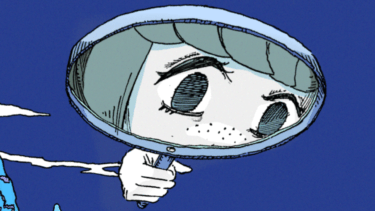華倫変先生のカリクラがこのたび復刊されます。華倫変先生は2003年に夭折した漫画家で、「カリクラ 華倫変倶楽部」2冊、「デッドトリック」2冊、「高速回線は光うさぎの夢をみるか」1冊の計5冊の漫画が出版されています(なお、カリクラには講談社版と、太田出版からの復刊版があります)。2000年代にインターネットをしていた人たちにとっては、奇抜なホームページをやっていたことも記憶にあるかもしれません。
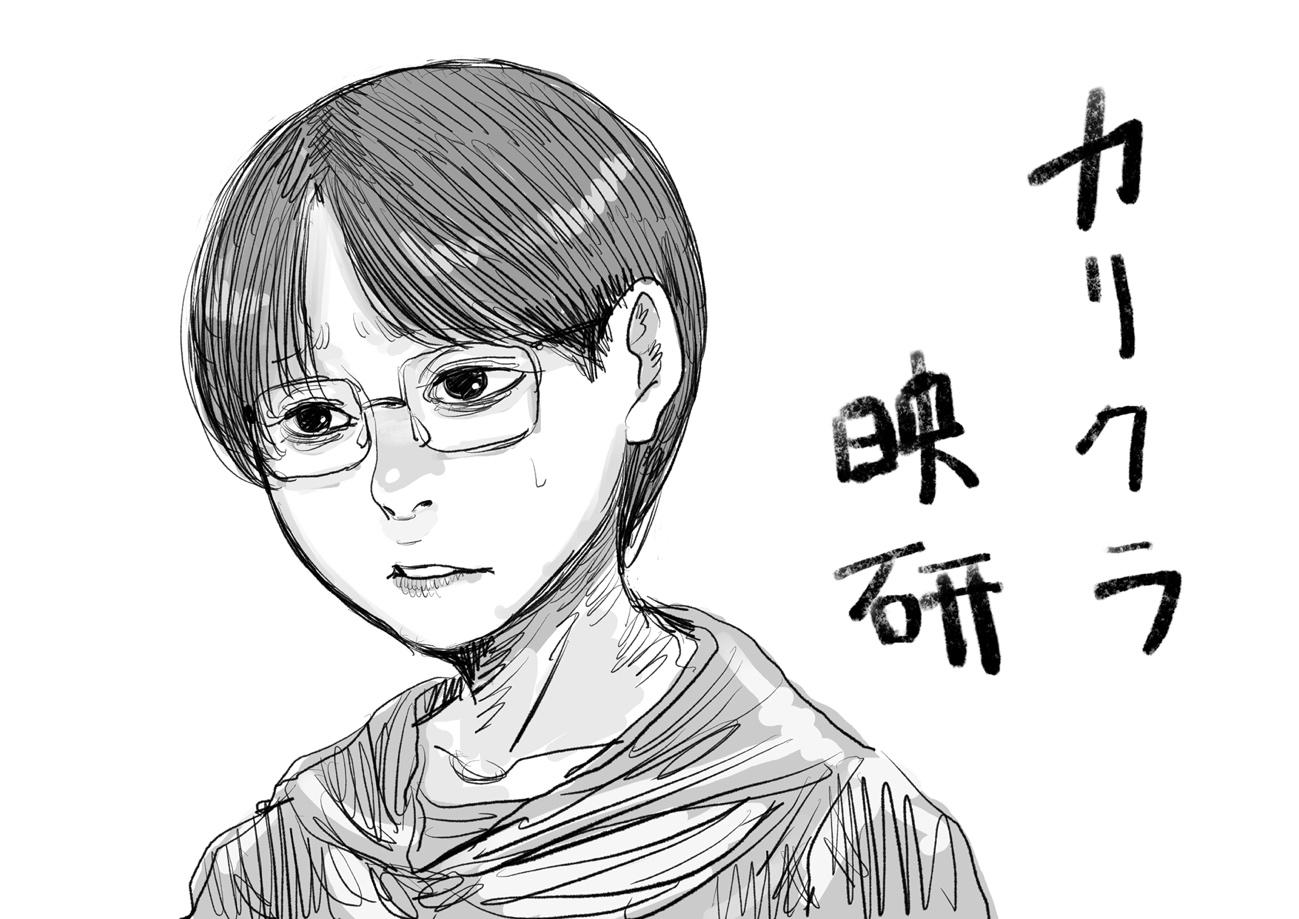
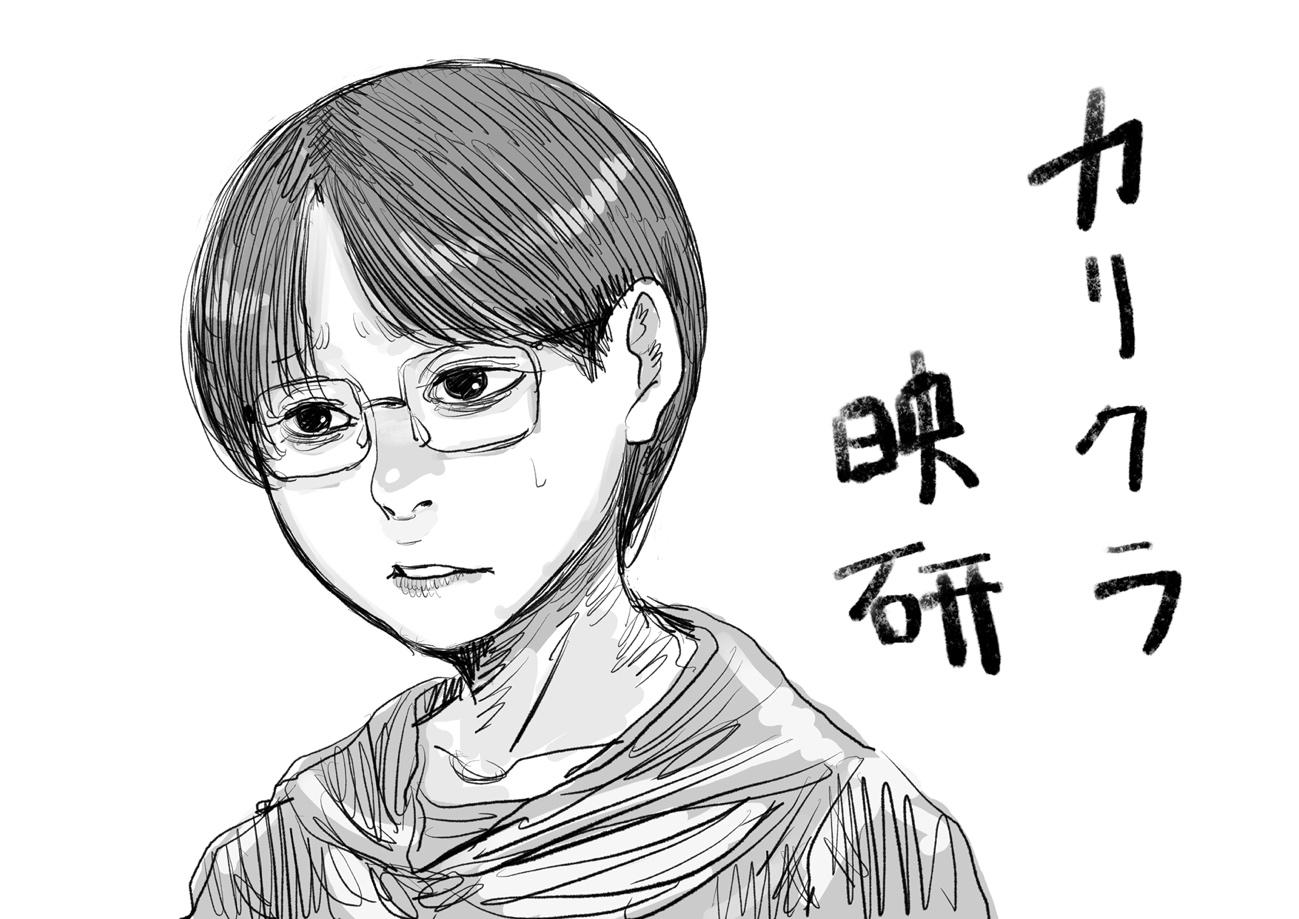
この度のカリクラの再度の復刊は、エロティクスfの再始動に合わせた太田出版の熱意のある編集さんの推進力により動いているものです。手前味噌になりますが僕も少し今回の復刊の手伝いをしました。その手伝いとは「華倫変先生の実家からカリクラの原稿を探すこと」です。
結論から言えば、ご遺族のご協力のもと、原稿は無事探し当てることができ、これまでモノクロでしか収録されていなかった絵のカラーでの収録や、ご実家に残されていたノートの一部の収録が、ご遺族の許可のもと収録されて「完本」として発行されることになります。
またこれによって東京で原画展が開催できることになりました。華倫変先生の原画を観られる機会は、熱意を持った誰かがご遺族の許可のもとで行う必要があるため、その条件がこの先のどこかで再び満たされるかどうかは分かりません。でも、少なくとも今回はあります。この機会を逃すわけにはいかないでしょう。
さて、この原画展開催に至るまでには流れがあります。
数年前、大阪の画廊モモモグラにて、華倫変原画展ができないかを考えた人たちがいました。しかし、そんなことができるのか?と思ったとき、画廊の人たちは太田出版から電子書籍が配信されるようになっていたことが思い当たったそうです。電子書籍の出版には現在の権利者との契約が必要です。ということは「権利は今も管理されており、太田出版ならばその連絡先も分かるはず」ということになります。
その後の細かい経緯は伏せますが、結果として、モモモグラで企画者を行っていた劇画狼さんが華倫変先生の実家に原画を探しに行くことになりました。そこでなんとか見つけられたのが「高速回線は光うさぎの夢をみるか」と「カリクラ 下巻」の原稿です。そのときには「カリクラ 上巻」の原稿を見つけることはできず、見つかった原稿のみを展示した「華倫変 没後20年追悼原画展」が開催されました。それが2023年のことです。
当時、僕はその話を聞きつけると、こんな機会は二度とないぞ!!と思って埼玉から大阪まで駆けつけました。自分がまだ十代の頃に読んでいた漫画の原画を、作者が亡くなってから20年も経って観られる機会がやってくるとは思わず、さらには色んなグッズも作られていて、わざわざ遠くまで行く価値があった原画展だと感じました(グッズは買いまくりました。当時はこんなことはもう二度とないのではないかと思いました。なぜなら、それだけの熱意を発揮して動いて実現する人が再び出てくるとは思えなかったからです。
しかし、「カリクラ 上巻」の原稿が見つからなかったということは、しこりとして残っていました。僕よりもずっとそれを感じていたのは探しに行っていた劇画狼さんでしょう。
そして今年、再び熱意のある人が現れました。かつて多くの人に影響を与えた雑誌エロティクスfの再始動を始めた太田出版の編集さんです。復刊する本をよりよい本にするために、上巻の原稿の捜索をする必要が出てきたのです。なお、前回復刊した際のデータは残っているため、原稿が見つからなかった場合でも復刊自体はできたと思います。ですが、カラー原稿がモノクロで収録されているページもあり、カラーでの収録のためには元の原稿が必要です。
そこで白羽の矢が当たったのが、かつて原稿を捜索した経験のある劇画狼さんです。そして、手伝いとして呼ばれたのが何を隠そう僕、ピエール手塚です。なぜ手伝いに呼ばれたかというと、僕が遠くから原画展にやってくる気のあるファンであったこととともに、現在、劇画狼さんと昨年大阪にオープンしたベアトラップギャラリーにおいて「イムリ大供覧展」の企画を進めており、その打合せのために大阪を訪れていたので、ちょうどいい人手として駆り出されたのでした。
おかげさまで原稿は見つかり、それ以外のネタ帳や絵の描かれたノートもご遺族から託して頂いたので、その一部は復刊される単行本の収録されることになるはずです。僕はそれを見させてもらうだけで手伝いに来てよかったなと思いました。
とにかく皆さんに覚えて頂きたいのは2点です。「カリクラ」が上下巻合わせた1冊として、これまで収録されていなかったカラーページや絵を収録して復刊されること。そして、華倫変先生の生の原稿が見られる原画展が東京で開催されることです。
ここからは、華倫変漫画が今なお多くの人に愛され続けていることについて、その理由の僕自身の見解を書いていこうと思います。
近年、人と話していて驚くのは、リアルタイムでは読んでいない世代と思われる若い漫画家や漫画家志望者の中に、華倫変漫画を愛好する人や、その影響を公言する人が多いことです。ただし、この「多い」というのはあくまで僕が話した範囲で何人もいたという意味で主観的はありますが。
時代を超えたファンがいる理由の僕の見解としては、華倫変漫画が、「漫画の物語として求められがちな形式を逸脱しておきながら、それでいて面白いことが分かるから」ではないかと思います。
漫画家は、漫画を描くときに、ある程度の守った方がいいルールを意識しがちだと思っています。とりわけ商業媒体で創作をしていくということは、読者の飲み込み易さのために、作るものをある程度の一般的な形式の型にハメることを求められ、だからこそ、その型の存在を強く自覚してしまうものだと思います。
そのために、そこを逸脱しながら面白いということが羨望の対象となるのではないでしょうか?自分の迷っている森の中で、知らない道筋があることを見せてくれるからです。
華倫変漫画で描かれる「人と人の噛み合わない会話」「喋るほど好感度が下がる登場人物」「コミュニケーションの成立ではなく断絶を描く様子」「物語の最初と最後で何も変わらないどころか、真綿で首が絞まるような中に埋没していくような結末」「しかしながら、根底に流れるセンチメンタリズムとある種の楽観」、そこには自分もこんな漫画を描きたいと思ってしまうような滋味が溢れているように感じます。
商業漫画において、お話は基本的にハッピーエンドの方がいいと僕は考えています。その理由は、「ハッピーエンドの方が、読者が良い気持ちになって得をしたと感じる」ことが多いと思うからです。商業漫画を、お金を貰うサービス業だと考えた場合、気持ちよくなれる漫画の方がお客さんの期待に応えているのではないかと思います。その方が商売は続きやすいでしょう。
でも、漫画を描く人、特にまだ漫画家志望の人はバッドエンドを描きたがることがあります。それは、ハッピーエンドがご都合主義に思えてしまうことや、現実はそうは上手くいかないということを描くことにこだわってしまうからではないかと思います。あるいは世の中にハッピーエンドが溢れていることへの反抗の精神かもしれません。しかしながら、不快感を伴うバッドエンドで読者を楽しませることは、ハッピーエンドよりも難しいと思います。
中途半端なバッドエンドを描いてしまうと、それはハッピーエンドにする努力を怠っただけの投げっぱなしにも見えてしまうからです。少なくとも編集者からはそう思われて指摘が入ることが多いように思います。
ここにおいて、華倫変漫画は不思議に読後感の良いバッドエンドを描いているというところが特異なポイントではないかと思います。起こった出来事だけを追うと人がただただ不幸になったような話で、その先に続いていく特によりよくもなっていきそうにない日常の中に心地よさを感じます。自分がやりたくで上手くできないことをやっている人がいるとなったら、そこには憧れが発生するものでしょう。
今回の原画を探す過程で見たのは、原稿に同封された編集者からのコメントやその内容への対応、漫画を描くための写真や他の漫画の大量のスクラップ、たくさんのプロットノート、そして、絵の練習を行い続けていた形跡です。
それらを見る中で、華倫変という人は、持ち合わせていた特異なセンスによって漫画を描いていた人ではなく、少しでも面白いものを作ろうとして試行錯誤を続けながら漫画を描き続けていた人だったんだなという理解になりました。少しでも面白いものを作ろうと編集者と試行錯誤を続けて描かれたのがカリクラだったのだなと思いました。
原画展ではその一端を見られるかもしれません。なので、2025年5月23日(金)〜5月25日(日)に代官山のUPSTAIRS GALLERYに急げ!5月27日(火)発売予定の「完本 カリクラ 華倫変倶楽部」の先行販売もあるそうです。
https://www.ohtabooks.com/publish/2025/05/23202500.html