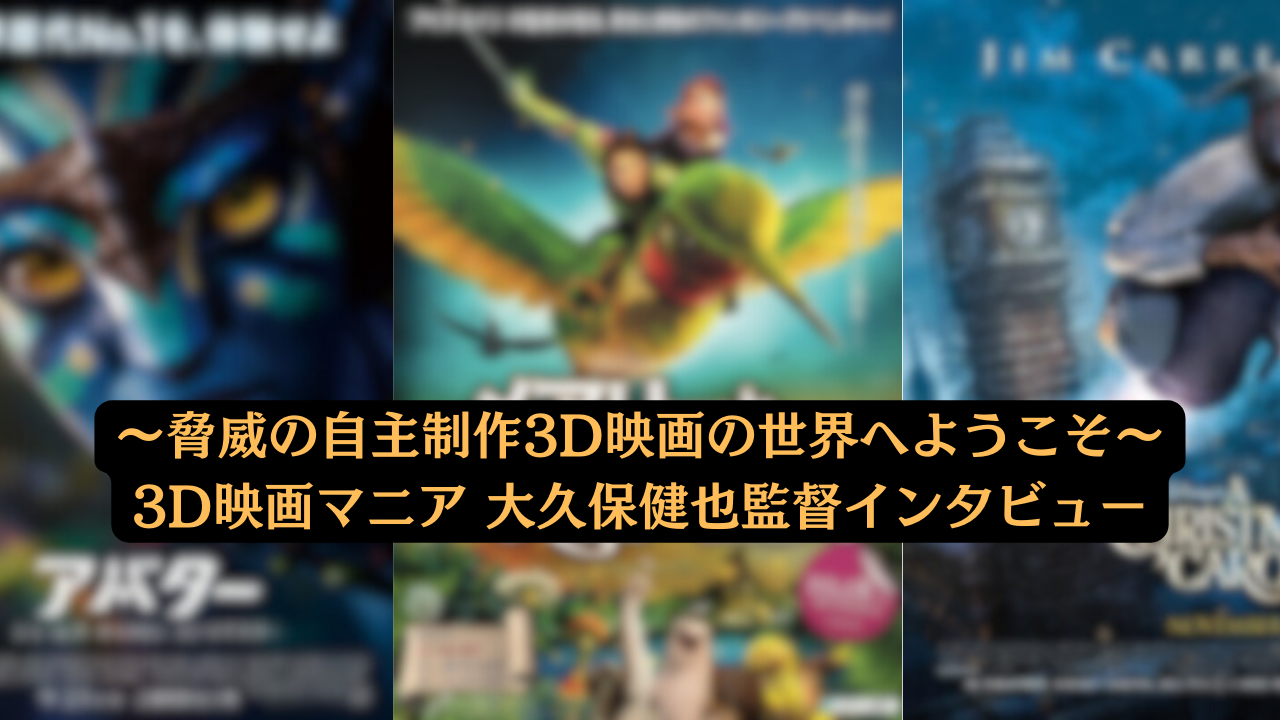「日本で3D映画を自主制作で作った人がいるらしい」。そんな噂を聞いた私はいてもたってもいられなくなり、さっそくインタビューしてきました。
その人物はなんと、映画感想サイトFilmarksに異常な熱量で3D映画のレビューを投稿していた人物でした。3D映画の歴史を過去から現在まで、そして個人でできる3D映画の作りかたまでを縦横無尽に語りまくる3D映画オタク必読(?)の12000字インタビューです。
1995年生まれ大阪育ち。中学時代より自主映画の制作を始め、60本以上の映像作品を手掛ける。数多くのインディーズアーティストのミュージックビデオの演出を経て、初の長編自主映画『Cosmetic DNA』(2020)が、ゆうばり国際ファンタスティック映画祭で北海道知事賞、ハンブルグ日本映画祭でジャンル作品特別賞を受賞、全国劇場公開される。他の監督作に『令和対俺』(2021)、『弄便』(2022)などがある。最新作は自主3D映画『害魚』。
3Dへの熱量
――監督のことを知ったのが、なんかヤバいfilmarksの人がいるって友人と話していて、絶対この人業界の人だって話になり、それでめちゃくちゃストーカーみたいに監督の存在を知りました。
↓大久保監督の熱量に圧倒される『アバター』filmarks
https://filmarks.com/movies/105148/reviews/141677764
(大久保監督)観た直後の感覚を忘れないようにっていうレベルでしか書いていないんですが……。
――ネットに転がっている3D映画のレビューとか見ても、飛び出てきたーみたいなレベルしか書いていないのに監督の文章にはマルチリグが、コンヴァージェンスポイントが、右目と左目の調整が、、みたいな……何か3D映像の業界の人なのかなって思っていました(笑)
どうして3D映画にそこまでハマったんでしょうか?
自分は1995年生まれなんですけど、明確に映画監督になりたいって思ったきっかけが中学時代の『アバター』(2009)の劇場3D体験だったんです。あれを観た時に「これこそが映画だ」みたいなヘンなスイッチが入って。当時は漫画家か小説家になろうみたいな感じだったんですが、全身が熱くなって鳥肌が立って「将来は映画監督になろう!」みたいな(笑)ちょっと前の世代のスター・ウォーズ的な熱狂ですよね。
――主に劇場で映画を観に行ったときがちょうど3Dブームだったんですね
そこから中高校生という多感な年齢の時期にガーッと2010年代前半から半ばくらいまでの3D映画ブームの作品群を浴びるように観ました。『ヒックとドラゴン』(2010)、『ピラニア3D』(2010)、『マダガスカル3』(2013)、『ヒューゴの不思議な発明』(2011)、『タンタンの冒険/ユニコーン号の秘密』(2011)『貞子3D』(2012)等々……。死ぬほど感動した3D映画も「なんだこれ」っていう3D映画もありましたが……。
それで20歳前後から本格的に映画監督を目指していろんな映像制作をしてきたんですけど、根っこでは3Dこそが映画のスタンダードだとずっと思っていました。映画に熱中するようになる前から寄り目で見ると浮き出る3D絵本とか、雑誌の付録のアナグリフ立体写真が好きだったというのもあって。
だから妥協として2Dで映像を撮ってるみたいな感覚がいつも多少あって、撮れるものなら全部3Dで撮りたいなとずっと思っていて。それをいろんな人に言ってるんですが賛同者はほぼ誰もいない(笑)


――最初に映画撮ろうとしたときは3Dで撮っていなかったんですか?
僕は中学一年生あたりに初めて映画を撮ったんですが、その頃はまず3Dの原理すらわからなかったですし、高校時代に発売されたソニーの3Dカメラ(HDR-TD10)は高すぎるし……で今になると中古で50000円くらいで買えるんで、ようやく……って感じです。
初長編監督作の『Cosmetic DNA』も準備段階で3Dで撮りたいと思った時期もあったんですが実現せず、平面の中でいかにスクリーンの奥のレイヤーを意識してもらえるかと考えながら編集時に画面をデザインしたり。
そこで『ゴーストバスターズ』(2016)で採用されているフレームブレイクという、シネスコ画面からビスタ枠まで映像の一部が飛び出るという手法を2D画面上ではありますが実験的に取り入れたりもしました。このフレームブレイクは最新作『害魚』でも一部採用しています。
最近はPSVRを手に入れて3D Blu-rayを観れるようになり、ここ半年くらいまとめていろんな3D映画を観て「次はこういう3D映画を撮りたいな」といろいろ想いを馳せています。PSVRは画質はやや残念ですが大画面での劇場の感覚を思い出せるという利点もあって。
――PSVR2で3Dの機能がなくなったらしいじゃないですか…?
ほんとに最低最悪な……。でもAppleがApple Vision Proの発売と併せて3D映画の配信を始めるという話があって、3Dブームの追い風になったりしないかなと……。
――ちょっと是非このあたりでまたアルフォンソ・キュアロンに3D映画とか撮ってほしいですよね
本当に映画表現として3Dでやれることはまだまだ無限にあるはずなのに、作り手も観客も2010年代の粗悪な3D映画の「目が疲れる」とか「ああ…こんなもんか」の印象から抜け出せていないのが良くないと思っています。『アバター ウェイ・オブ・ウォーター』(2022)でガーっと3D映画ブームがまた到来すると思ってたんですが……。
――(笑) これは3D映像会社の方に伺ったんですが、2011年に3.11があり、業界的に3D的な娯楽は避けようって流れになり、そこで3Dの企画がいくつも無くなったらしいんですよね。ちょっと日本の3D的な娯楽への忌避を感じてしまいます。ただ単に飛び出したり奥行を楽しんでいいのだろうかっていう。
自分も数年前に監督作を劇場公開したという実績ができた流れで、いろんな人に「3D映画を撮りたい!」って企画を送ったりしていたんですけど、今の日本に3D映画は必要ないって言われたりして。まあ、今の日本で3D上映ができるのはほぼシネコンのみなので低予算映画じゃ難しいのは当たり前なんですが。いつか低予算映画でもドルビーシネマで3D上映される、そんな時代が来たらいいですね。
余談ですが、ドルビーシネマといえばアン・リー監督の『ジェミニマン』(2019)のハイフレームレート3D上映は本当にすごかった。爆発シーンが本当に画面の奥で爆発が起きているようにしか思えないぐらい生々しくて、銃のマズルフラッシュとかも肉眼だとこんな風に見えるのかという感動があったり。あのマズルフラッシュを観て以来、一般的な映画の24FPSのマズルフラッシュは全部ちょっと嘘臭く見えるようになってしまいました。
フルスペックの120FPSで上映している劇場は当時日本で3館ぐらいしかなく、しかも興行的にアレだったのか10日間くらいしか上映してなかったんです。4回ぐらい通いました。


――アン・リーやジェームズ・キャメロンが推し進めている3D+ハイフレームレートという上映形態についてはどう思いますか?
構築した異世界を丸ごとハイパーリアルにフレームレートをあげて映したいという二人の感覚はすごく理解できます。モーションブラーが減って3Dの精度もあがりますし。
でも僕は全ての映画がそうあるべきだとは思っていなくて、映画表現技法の選択肢の幅が広がるという意味で賛成です。まだまだハリウッドでも一般的な考え方にはなってないと思うんですが『スパイダーマン:スパイダーバース』(2018)は12FPSで『ジェミニマン』は120FPSみたいな状況はすごく健全だと思っていて。
24FPSでしか伝わらない情感や雰囲気があるのと同じく12FPS、48FPS、120FPS等それぞれ特有の強みや弱みがあって。このストーリーを語るにはどのフレームレートが一番適切なのか、このキャラクターの感情は何フレーム単位で変化しているのかという、そういう議論をもっと企画段階でする映画があってもいいんじゃないかという。
更に言うと、ひとつの映画のなかでアクションシーンは48ないし60FPS、その一方でコミカルだったり戯画的なシーンやショットは12フレームに落とすみたいな描き分けや、ひとつの感情が盛り上がっていくのに呼応するようにフレームレートも徐々にあがっていく、みたいなグラデーション描写をし、その作品を60フレームでパッケージして上映するみたいなことは技術上全然できるじゃないですか。セルアニメってそういうことしてますし、キャメロンも今僕が言ったニュアンスとは少し違いますが24~48FPS間で軽くしてますよね。
ひねったプロットやカメラワークもいいんですけど、新しい表現ってそういうところからも生まれる気がします。映画ってそもそも文学や絵画と違ってテクノロジー・アートなんで「映画はそういうものだから」っていうしきたりだけで24FPSの世界に縛られるのはもったいない。
この間『タイタニック』の3Dリバイバル上映があったじゃないですか。そのときに劇場で観返して初めてキャメロンってフィルムがいいとか、3Dがいいとかは究極考えてない気がしたんですよ。
自分のビジョンを最も的確に具現化するためにここはミニチュア、ここはCG、ここはセットと、あらゆる手法を検討して忖度なく最善の方法であのスペクタクルを作ってるってことに感動したんですよね。キャメロンというとCGのイメージが強いですが、別にCGが好きなんじゃなくて表現したいものの果てにパフォーマンス・キャプチャーがあっただけなんだという。これは『アバター』の話ですが。あの人はやっぱり「映画はそういうものだから」を信じず、常に疑いながら表現しているなと思いました。しかもあの年齢で。ヤバい人ですよね。映画人のあるべき姿だと思います。
ところで48FPSはよく「安っぽく見える」みたいな意見がありますが、それは衣裳や美術が無意識のうちに「24フレームレートで撮影される前提で」作られたからなんだと思います。カメラの動かし方、編集も然り。そういう部分は『ホビット』シリーズ(2012~2014)にも『ジェミニマン』にもあって。ハイフレームレートという撮影手法自体が安っぽいのではない。作り手のビジョンやストーリーがフレームレートに追いついていないんだと思います。
例えばユニバーサル・スタジオ・ジャパンのハリー・ポッター・アンド・ザ・フォービドゥン・ジャーニーは120FPS映像ですが、あれを観て「安っぽい」とは誰も思わないはず。ハイフレームレートという技術自体に問題があるわけではない何よりの証拠です。


――よくできた3Dとよくできていない3Dというお話がありましたが、監督の中でその3Dの評価基準について教えて頂いてもよろしいでしょうか。
よくない3D映画として『アバター』公開直後に多かった「とりあえず3Dは金になるらしいぞ」レベルの志で3Dコンバートされたものがまずひとつ。そもうひとつは完全にストーリーのテンションと3Dの立体感のそれが調和してない映画。観客が見て「これは2Dで観てもいいんじゃないか」って思う原因のほとんどはこれな気がします。
とりあえずやってみた系の前者は今はほぼない気がしますがシンプルに害悪だなと思います。この手の映画は3D映画そのものだけでなく、3Dコンバートという技術自体も悪だという価値観を生んでしまいました。コンバートも使い様で、全編コンバートの3D映画にも素晴らしいものはたくさんあります。
後者は優秀なステレオグラファーが現場にいるけど監督やスタッフがストーリーテリングツールとしての3Dにあまり興味がない場合にできる映画なのかなという気がします。何にせよ両者とも「この色はどういう感情を想起させるか」みたいなことを知らない人間がカラー映画を撮って、これならモノクロでいいじゃんって言われているような感じではないでしょうか。
――目が疲れるような3D映像が忌避される一方で、ある程度飛び出し映像を見せないと3Dの意味がないって言われてしまう。これは監督にとってなかなかのジレンマだなって思うのですが、監督は視差が強ければ強い方がいいのか、観客の目に優しいことを優先すべしなどの信条はお持ちでしょうか?
僕は日常的に3D映像を観ているので一般の人がどのレベルの視差のものをどれぐらい観たら疲れるのかがわからなくなっているのでなかなか難しい(笑)
3Dで視差が強い弱いとはまた違うかもしれないですけれど、3D映像にすごく効果的なアングルでの撮影だったり、演出としてステージングが組まれていれば視差が多少弱かろうが観客満足度の高い3D映画にはなると思っていて。そのへんに関して圧倒的に抜きん出て天才だなって思っているのがロバート・ゼメキス監督です。
『Disney’s クリスマス・キャロル』(2009)とか『ザ・ウォーク』(2015)とかって別にそんなにガチガチに視差が強いわけではないんです。でも人や物の配置、ライティング、カメラワーク、シーケンスの流れ、あらゆる要素がすべて立体的。自分も舞台にあがって舞台を間近で鑑賞しているような感覚。しかもこういう構図のショットはステレオ撮影せずに2D撮影、後に部分的にコンバートして印象付けたい被写体だけ過度に立体化する、みたいなことまで全部演出として意図的に行われていて、その全てがドラマの推進力になっている。
映画の歴史の中でなんとなくこういうふうに撮影したらこういうふうに撮れるだろうってものがあるじゃないですか。でもそれってひとつのレンズのみの2D撮影由来の発想のものでしかなくて、3Dカメラで撮ったらこうなるんだってノウハウが世界的に足りなすぎるって僕は常々思ってるんです。
でもゼメキスにはそれがある。完璧な3D映画が撮れるから逆説的に『フライト』(2012)のような完璧な2D映画も撮れる。最高の映画作家だと思います。すみません、話が逸れました。


――監督って3D映画についての体系的な知識が物凄くあるように思うんですが一体どのような勉強をされていったんでしょうか?
いろいろありますが『3D世紀』って本があって。あれは発売した当時なかなか買えなくて高校の帰りに立ち読みしてて。最近ちゃんと読みましたがすごく勉強になりました。
――あれはとんでもない本ですよね。
いつか是非著者の大口孝之さんに一度お会いしたい……。


――ほかに読まれた文献とかありますか?
『アバター』公開以降に3Dに関する研究や分析が活発になったっぽく、その時期の論文とかは最近の『害魚』での3D撮影に向けて読み漁ったりしました。あとは『塔の上のラプンツェル』(2010)や『トランスフォーマー/ダークサイド・ムーン』(2011)のステレオグラファーの方々のインタビュー等は凄く興味深くて。『塔の上の~』は3D技術的にとんでもないことをしている作品で、前景、中景、後景それぞれ異なるレンズ幅でステレオ撮影し、それを合成することで無理なく被写体に立体的な厚みを持たせることができる「マルチリグ」という手法を採用していて。ああいうことをいつか実写3D映画でできたらと思いますね。近しいことを『スピード・レーサー』(2008)が違う意図でやっていますが是非3Dでやってみたい。
――そういうのを聞くと現実をアニメの撮影台にもう一度編集によって戻して思考するのが3D的な考え方だなって思いますね。
そうですね。そういう意味で元来3D映画に向いている思考方法の監督と向いていない監督がいると思います。大雑把に言うと「カメラ対現実」みたいな発想がベースの作家の人は向かないんじゃないかと思います。でも、そういう感覚の人が撮る3D映画もまた面白かったりするんですけどね。ギャスパー・ノエ監督の『LOVE 3D』(2018)とか。
次のページではインディペンデント3D映画はいかに撮られたのか!? 伺っていきます!
- 1
- 2