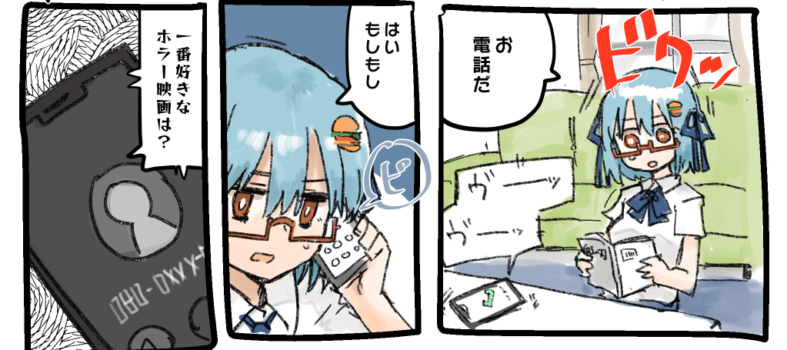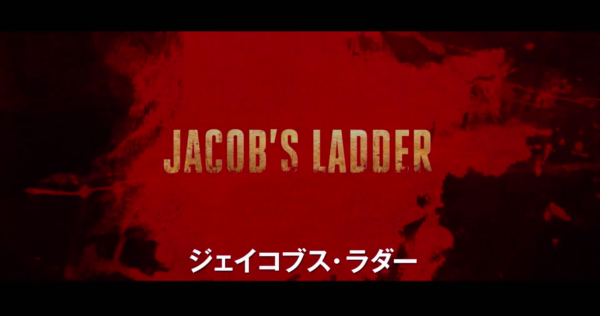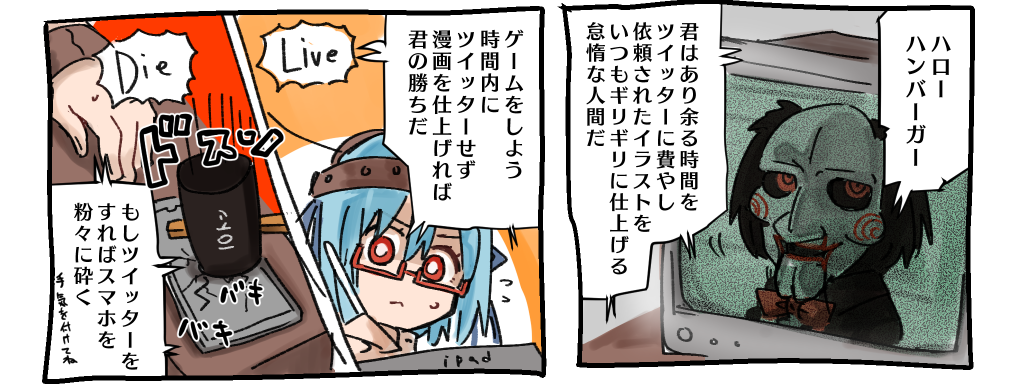「ハイブリストフィリア」と「赤い部屋」
人間は常に「暴力を見たい」という欲望を抱えてきた。現代はともかく、娯楽のない時代は特に。
犯罪者に恋い焦がれる”グルーピー”は20世紀を通じて沢山記録されてきた。1930年代には銀行強盗カップルのボニー&クライドが熱狂的に報じられ、彼らに憧れる若者が全米に現れた。80年代には連続殺人鬼テッド・バンディが裁判中に女性からのプロポーズを受け、獄中にも大量のファンレターが届いた。日本でも同様の例は枚挙に暇がない。
こうした現象や心境、嗜好を「ハイブリストフィリア」と呼ぶ。
その誰もが犯罪行為自体を肯定している訳でないはずだ。それでも、犯罪者に惹かれてしまう衝動は、ただ異常と切り捨てるにはあまりに普遍的に、一部の人々の間で繰り返され、顕在化してきた。
一方で、「赤い部屋(Red Room)」という都市伝説はインターネット黎明期に生まれた。拷問や殺害がリアルタイム配信されるサイトというある種の都市伝説である。日本では1990年代末のFlash黎明期に同じようなブラクラサイトがある。現実にあってほしくはないが、あの混沌としたインターネット黎明期を思い出すと「あり得ない」と切り捨てることもまた、難しい。
犯罪者を「推したい」欲望と、暴力を「見たい」欲望。『RED ROOMS レッドルームズ』はこの二つを同時に描き出す。つまり本作が暴くのは、加害者でも被害者でもなく、「暴力的な映画を見たい」と願う私たちそのものである。
主人公ケリーの不気味な視線を追う


モントリオールで開かれている連続殺人犯ルドヴィク・シュヴァリエの裁判。少女を残虐極まりない方法で拉致・拷問し、死に至らせ、その映像をインターネットの闇サイト「レッドルーム」で配信したとされるショッキングな事件は世界的な注目を集めている。
その裁判に取り憑かれたように通い続けるのが主人公ケリー=アンヌ。彼女はモデル業が務まるような美貌を持ち、仮想通貨で巨万の富を築き、独自にAIまで開発してしまう非の打ちどころがない万能な女性に見える。だが富や才能、美貌では彼女は全く満たされた様子がなく、連絡を取る相手は仕事相手だけ。そんな彼女の日々の楽しみは、まるで浮浪者の様に裁判所の前で孤独に寝泊りし、殺人事件の裁判を傍聴することだ。
傍聴席でケリーが出会うクレマンティーヌは、被告の無実を信じる無垢な信者。彼女とケリーは正反対でありながら同じく犯罪者を崇拝するハイブリストフィリア的な嗜好に駆られたグルーピー的絆を結ぶ。
だが、ケリーが未発見だった最後の被害者のスナッフフィルムを闇サイトから競り落とした時から、彼女達の求めるもの———人としての本質は全く違っている事がわかっていく。”ホンモノ”と熱狂に駆られただけの”信者”との対比が描かれ、ケリーは傍観者の一線を超えていく。
暴力の「不在」が孕む暴力


本作最大の特徴は、暴力そのものを一切映さないこと。
映るのはそれを見つめる主人公ケリー達の眼差しである。冷たいブルーの画調、無機質なフレーミング。撮影監督ヴァンサン・ビロンによる静止画のような構図が、観客を“傍聴者”の位置に固定する。
音響はさらに徹底している。作曲家ドミニク・プラントの低音と沈黙が、画面の登場人物だけが見つめる、不在の残酷さを増幅する。わずかな環境音や沈黙の間合いが、観客の想像を強制的に膨張させる。
暴力シーンを一切見せないことで想像力を掻き立て、品が良いままより最悪な表現をするという手法で、一番記憶に新しい映画は監督ジョナサン・グレイザー『関心領域』(2023)がある。歴史的な背景を知っていれば知っている程落ち込んでしまい、歴史的背景を何も知らない人には血の一滴も流れていないように見える凄まじい構造の映画。見せられている部分はただ静かな映像で、暴力は常にオフスクリーンで行われているという点で今作と共通点がある。
本作、『RED ROOMS レッドルームズ』では戦争のような大規模な暴力は描かれない。戦時のナチスのユダヤ人大虐殺を描いた『関心領域』と違って現代社会のシリアルキラーという個人、被害者という個人、そしてそれに関心を寄せる個人。凄惨な犯罪事件ではあるが、戦争に比べると何もかもミニマムだ。しかしそれをつなぐのは膨大なインターネット。誰でもアクセスできる闇サイト、伝説の「赤い部屋」戦争より圧倒的に被害者は少ないのに、より身近な”スクリーンに映らない暴力”が想像し易くなっている。
「見てないのに、見てしまった」という不快。本当に良い意味で硬直した不快な劇反。不快な直視型スプラッタの嫌悪とは異なる、想像を強制される事により湧き起こる不快こそが本作の核心である。
ケリー=アンヌという鏡


主人公ケリー=アンヌのキャラクターは非常に現代的だ。美しいが感情がないロボットの様な印象を受ける。何を考えているのか全く顔にでない、無機質な雰囲気。社会的には成功している“万能人間”であるにもかかわらず、彼女の感情は暴力でしか揺れ動かない。
彼女が涙するほど高揚するのは数回だけ。例えば、裁判で被告から手を振られた瞬間。例えば、闇オークションで“最後の被害者が動画”を落札した時。
ケリー自身は誰にも暴力をふるわないにもかかわらず、ケリーはあくまで「暴力を見るだけ」ではあるが、その暴力への興味関心はどんどんとエスカレートし、最終的に連続殺人鬼である犯人よりも不快に思える。そのケリーに一番近い存在がいる。それは、この映画をただじっと見ている我々だ。
と言ってしまうと「こんな異常な女が自分である筈がない!」と思う視聴者の方は多いだろう。ケリーは最終的には「ただじっと見ている」に留まらない異常な行為を次々とやってのける。それこそ、人を殴ったり刺したりはしないものの、”直接的な暴力に繋がる事以外の不謹慎な行為”はほぼ全てやっている。お手製のAIを物理的にミキサーにかけて破壊するシーンは象徴的だ。そして最後に被害者の衣装を身に纏い、被害者の遺族の家に忍び込む――これはもう完全に”ラインを超え”ている。「見る」だけではなく被害者と加害者ではない、第三のサイコな存在、異常な被害者への同化願望の極北である。
一体何が彼女をそうまでさせるのか。彼女がここまで執拗に暴力に惹かれるバックボーンは描かれず、同情できる過去もない。私はここが非常に現代的だと思う。つまり彼女はインターネットやSNSなどで無責任に世界中の悲劇を臨む、現代の無責任な目線の集合体の擬人化なのだ。
『ファニーゲーム』(1997)との類似と差異


『RED ROOMS レッドルームズ』を見て、サスペンス映画好きの多くが思い起こすであろう作品がある。ミヒャエル・ハネケの『ファニーゲーム』だ。あの映画は観客を挑発し、暴力を娯楽として消費する視線を露骨に断罪した。
筆者の人生ベスト3に入る大好きな映画。『ファニーゲーム』では、子供は殺され、非力な女性は性的にも精神的にも凌辱され、成人男性は前半に怪我をさせられ、反撃の希望はことごとく折り続けられ、誰も生き残れない。「これだけは見せないでくれ」と我々が思う想定される限りの不快で理不尽な暴力が起こり続ける。しかし視覚的な暴力描写は全て映されず、ただ絶望する登場人物の表情だけが大写しにされる世間的には”胸糞”とよく称される映画だ。
監督のパスカル・プランテはこの『ファニーゲーム』から『RED ROOMS レッドルームズ』の着想を受けたということだ。私は”当たった”気持ちになり、大変嬉しくなってしまった。この映画は、『ファニーゲーム』に感銘を受けたクリエイターのハネケへのアンサー的な作品だと思うと更に腑に落ちるからだ。
『RED ROOMS レッドルームズ』も『ファニーゲーム』も、また観客の好奇心を無責任なフィクションの暴力への共犯者として扱うが、その手法は対照的。
『ファニーゲーム』の加害者は暴力の擬人化的な表現であり、思想ある個人ではない。むしろ、様々な暴力映画で感情を無視され派手に血を流されながら無限に虐げられた被害者———その感情や悲痛に寄り添う慈しみを感じる。暴力の擬人化的な男性二人はまるで暴力描写にエンタメ性を見出す我々だと思わされ、自身のエンタメへの向き合い方を考えさせられる作品。
一方、『RED ROOMS レッドルームズ』は加害者も被害者も主役にせず、暴力を完全にオフスクリーンに追放し、暴力に関心のある部外者、つまり我々視聴者に近い存在が主人公とされる。加害さえしない、更に遠くから暴力を追う無責任さを突き付けられる。『ファニーゲーム』より現代的な、インターネットなどを介した安全圏からの無邪気で無責任な己の姿を突き付けられ、負けず劣らずの新しい不快さを創り出している。
配信時代の倫理


本作は北米ではストリーミングサービスShudderで配信され、大きな反響を呼んだ。「配信」という形式そのものがこの映画の追体験となる。
視聴者がケリー=アンヌと同じポジションに座り、クリック一つで「暴力を視聴」できてしまう構造だ。
「スナッフフィルムを無邪気に楽しむケリー」と「映画の配信ボタン一つで色々な暴力にアクセスできる我々」が重なる。だからこそ、本作は映画館で観るべきだ。暗闇の中に集められた観客が、同じ不快を共有する。その共同体的な経験は、孤独な視聴の欲望を外化し、他者の存在と共に意識させる。
映画館の座席に座る私たちは、まさに裁判の傍聴席に並んでいる。暴力を消費しつつ、他者と共に“ただ傍観する”。その構造自体が、『RED ROOMS レッドルームズ』のテーマと強烈に重なっている。
人々が「現実の暴力をクリックしてしまう」欲望はすでに何度も証明されている。例えばカナダで起きたルカ・マグノッタ事件では、殺害映像が拡散され、国境を越えて数百万回も再生された。『RED ROOMS』が描く群衆、ケリー、そして我々の異常とも言える暴力への興味は、現実社会に確かに存在する。
終わりに


『RED ROOMS レッドルームズ』は、「暴力に興味を持つ人間の無責任な欲求」そのものを主題にした映画である。暴力を映さずに映像美と沈黙を駆使し、観客の内部に不快感を無限に増殖させる。インターネットの発展、SNS文化、配信時代の倫理に伴った人間の露悪的欲望を徹底的に炙り出す。
ケリー=アンヌは逸脱したサイコな異常者だ。だが、我々の興味はサイコでないのだろうか? 異常な事件へ関心を一度も持ったことはないのか? ネットの向こうの見えない被害者をただ目線で凌辱したりした事が一度もないと言い切れるだろうか?
私達はラストシーンの悍ましいケリーの姿を、目を逸らさずに見届けるべきだ。その姿は日々インターネットで様々な暴力を消費する、私たちの鏡像なのかもしれないのだから。
作品情報と監督
監督はカナダ・モントリオール出身のパスカル・プランテ(Pascal Plante)。デビュー作『フェイクタトゥー』(2017)で若者の孤独を繊細に描ききった。第三長編となる『RED ROOMS レッドルームズ』は、彼が一貫して追い続ける「視線の倫理」をより拡張した総決算だ。
本作は2023年にカーロヴィ・ヴァリ国際映画祭でプレミア上映を開始し、続くファンタジア国際映画祭では最優秀作品賞、脚本賞、音楽賞などを受賞。自身もクリエイターである主演のジュリエット・ガリエピも高い評価を得て、ケベック映画賞で新人賞を獲得した。
監督・脚本:パスカル・プラント(『ナディア・バタフライ』)
出演: ジュリエット・ガリエピ、ローリー・ババン、
エリザベート・ロカ、マックスウェル・マッケイブ=ロコスほか
2023 年/カナダ/フランス語/118 分/カラー/字幕翻訳:橋本裕充
/G/提供:シノニム/配給:エクストリームフィルム
©Nemesis Films
公式サイト:redrooms.jp