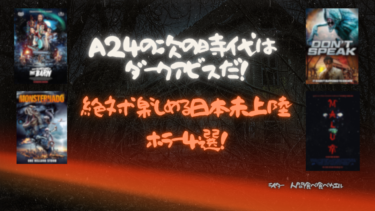『へレディタリー / 継承』、『ミッドサマー』とトラウマとなるような体験をさせてくれたアリ・アスター監督が新たなる映画を繰り出してきた!
2024年2月16日に日本公開を果たした『ボーはおそれている』はこれまでに体験させてくれた恐怖とはまたひと味違った恐怖体験となっていました。
これは夢か現実か?おじさんが主人公の『不思議の国のアリス』?
『ボーはおそれている』は端的に言ってしまえば“変な映画”です。
主人公は中年のおじさんでタイトルにもなっているボー。母のもとへ帰ろうとした矢先にボーはアクシデントに見舞われ、帰郷のための飛行機に乗り遅れてしまいます。電話でそのことを伝えたのを最後に、母親が事故により亡くなってしまったという連絡が入ります。こうして慌てて母の葬儀へと向かおうとするボーでしたが、そこからボーにとっての長い長い旅が始まります。
作中では冒頭から不可解な出来事が盛りだくさん。ボーが住んでいるアパートの周辺は異常なほどに治安が悪かったり、そんなボーの住むアパートの一室を人々は狙っていたりと、そもそもボーが正常な人間なのか。ボーが処方されている薬の副作用なのか。これが現実なのか夢なのか全くわからないまま、ボーの視点で不思議な出来事を巡っていくことになります。それはさながらおじさんが主人公の『不思議の国のアリス』。まともな指針が見つからない中でボーが抱えている問題が少しずつ明かされていきます。
重要なのはこの映画に「夢か、現実か」の問いに対するわかりやすい答えが明示されているわけではないこと。意味深長な物語の果てに明かされる“事実”はそれ自体が現実的とも言えない出来事となっており、この映画自体が一つの寓話だったのではないかと思わせます。
果たしてこの映画を観て呆気に取られるのか、「なるほど」と思えるのか。人によってその振り幅がかなり大きい映画なのは間違いないでしょう。
2つのアリ・アスター監督のしるし
『ボーはおそれている』はこれまでのアリ・アスター監督の作品とは毛色が違う映画にはなっているけれど、やはり紛れもないアリ・アスター監督作品だと思える要素で満ちています。
アリ・アスター監督作品恒例の暴力性
アリ・アスター監督の作品といえば、「この嫌な映像を見ろ!」と言わんばかりのショッキングな描写が登場することでもおなじみ。『へレディタリー / 継承』ではトラウマ級の起きて欲しくない交通事故描写が登場したり、『ミッドサマー』ではこれでもかと人が人体破壊の末に死にゆく姿が描かれたりと人を選ぶであろうグロテスクなシーンが唐突に挿入されます。それらの作品と比べると『ボーはおそれている』はその類のショッキングな映像は少ないと言えます。そういう意味では比較的、オススメしやすいアリ・アスター映画とも言えます。
それでもなお、この映画がアリ・アスター作品だと思わせるのは起こる事件にはやはり生き死にが関わるものばかりで物騒だったり、作中の随所に死体が登場したりと描写としての一撃はこれまでの作品ほどでなくとも、あいかわらず映画の内容は一貫して不穏です。
冒頭、ボーがカウンセリングから家へ帰る帰路で今にもビルから飛び降り自殺を図ろうとする人物が登場。この人物が死んだのかどうかは全く描かれないのですが、このようなモヤモヤした出来事は大小あれど絶え間なくボーと、映画を観ている私たちに積み重なっていきます。
アリ・アスター監督作品恒例の親族との因縁
もう一つ忘れてはいけないのが、アリ・アスター監督作品のテーマとして親族との因縁が必ず物語のキーになってくる点です。『へレディタリー / 継承』では亡くなった母の信仰が娘や孫たちを悲惨な目に合わせることになる映画でした。『ミッドサマー』は妹が両親を殺害したことが発端として物語が始まっていき、その末に地獄のような体験と心境の変化を迎えていきます。そのどれもが親族に対するネガティブな“事件”が映画を動かしていくのですが『ボーはおそれている』もその例に漏れない映画であるどころか、母親との因縁がよりテーマとして色濃く出た映画になっています。
どうにかして母親の葬儀に出席したいボーとどういうわけかそこへたどり着くことのできないボー。本人は母親のことを大切に思っているような描写は映る一方で、その随所には決してボーが母親との関係が良好というわけではなかったような描写も挟まれ、その微妙な距離感になんらかの問題を感じさせます。
そしてボーがその旅路を終えて母親の死を間近にした後に起きた出来事と、ボーの旅路に隠されたある秘密が明らかになった時、ボーが抱えていた問題が冒頭よりも具体的に浮かび上がるようになります。
『ボーはおそれている』で実現したコラボレーション
アニメーションパートでは“あの”映画の監督が参加
一方で『ボーはおそれている』ではこれまでの映画にはなかった別のエッセンスが盛り込まれています。それがアニメーションパートです。
『ボーはおそれている』の中盤では劇中劇とでもいうような“ボーが歩んでいたかもしれない人生”がアニメーションの手法が用いられて描かれます。このパートはチリのクリストバル・レオン氏とホアキン・コシーニャ氏が制作に参加しています。お二人は2023年に日本でも劇場公開を果たし話題になった『オオカミの家』(2018)を制作した監督のコンビです。
『オオカミの家』はピノチェト軍事政権下のチリで実在したコロニア・ディグニダをベースに、“ある施設”から逃げ出した少女・マリアが森の中で一つの家を見つけ、そこで二匹の子ブタと出会い世話をして暮らすのですが、そこへマリアを探すオオカミがやってくるというホラーアニメーション映画です。『オオカミの家』が凄まじいのは、いわゆるストップモーションアニメーションという手法で撮影された映画ではあるのですが、セットを組んで小型の人形などを動かして撮影するようなタイプのものではなく、部屋一室を舞台に壁を塗り替えたり、巨大な造形物を少しずつ加工していくことで、アニメーションを作り上げていくという異色のスタイルで制作されています。
この『オオカミの家』がアリ・アスター監督の目にとまったことで、今回の映画への繋がりが生まれました。
予習をしておくなら『オオカミの家』よりも短編『骨』?
一方で今回の『ボーはおそれている』内でのクリストバル・レオン氏とホアキン・コシーニャ氏の活躍は、その気配はそれほど強くなく、むしろ作家的な色を抑えたものとなっています。実際監督インタビューなどでは自由にやらせたというよりも、アリ・アスター監督の望むような画になるように制作に臨んでもらったようで、言われなければお二人の参加にはなかなか気づけなかったかもしれません。
そういう意味では予習をしておくなら『オオカミの家』よりも、今回の日本上映の際に併映上映を果たしたクリストバル・レオン氏とホアキン・コシーニャ氏によって制作された短編の『骨』(2021)の方がより近い気配が感じられそうです。
この骨という短編アニメーションは1901年に制作された世界初のストップモーションアニメ……という体裁の異色の作品。チリで発掘された映像には少女が死体を使った儀式の様子が記録されていたというもの。ここで蘇生させる人間は実在のチリの独裁政治に関わった人物であり、婚約を破棄する儀式の様子はチリの民主的な国家への移り変わりを反映させたものにもなっていました。
この『骨』の制作から製作総指揮にアリ・アスター監督の名前が並ぶようになっており、『骨』の少女が硬いお面のようなものを付けている様子は、劇中に登場した天使のようなキャラクターが付けていたお面とも重なるようで意味的な繋がりを感じられます。
惜しいのはこの短編『骨』は劇場限定公開作品となっていて、『オオカミの家』のソフトには収録されていない点。現在は視聴が困難な状態にあります。権利関係の問題で一時的な上映はできても、個人的に所有は難しいので待っていてもソフト化は当分難しそう。今後ももし『骨』の上映の機会があればぜひ貴重な作品として足を運んで観ておきたい作品です。
『ボーはおそれている』の楽しみ方
これまでのアリ・アスター監督にあったものがあれば、なかったものも盛り込まれた『ボーはおそれている』。そんなディテールも眺めながら観ていくと、理解や共感こそできなくとも鑑賞する際の軸とできるかもしれません。
そもそもタイトルが示すように『ボーはおそれている』ではボーの不安定な気持ちが映像化されているので、そりゃあお世辞にも親しみやすい作品とは言い難いのです。監督は本作を“ボーを体験する映画”と謳っている通り、ボーが精神的に不安定なのでその体験が理路整然としてないことの方が必然です。そういう意味でもまさに悪夢的なおそろしい映像体験が待っていると言っても過言ではありません。その唯一無二っぷりを浴びに……いや、浸かりに『ボーはおそれている』へ足を運んでみてはどうでしょうか。