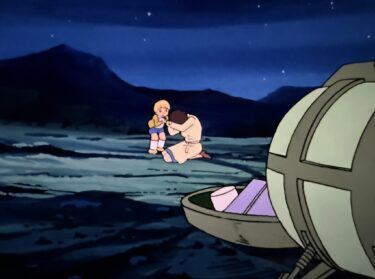皆さんは「100日後に死ぬワニ」覚えてますか?
100日後に死ぬというかなり気になる煽りと、毎日更新という事で「ワニが本当に死ぬのか?」というのを画面のこちら側で感じられるリアリティショーみたいな部分で社会現象にまでなってましたね。
ですが、掲載終了直後に単行本やメディア展開を発表した結果様々な憶測を呼んでなんだか残念な終わりを見せましたね。その後も憶測や決めつけが終わらず作者のきくちゆうきさんが信じてもらえず残念という内容の声明まで出す始末…。
なんだかあれで冷めてしまったという人も多かったのではないでしょうか。実際、感想を言い合うような雰囲気は無かった気がします。
そんな中で発表された映画版の方は覚えてますか?
実際「映画がそんな早く作れるはず(企画が動くはず)ない」等の言葉を引き出すきっかけになったり、前述の冷めた空気があったりして「触れるのもなんかな…」っていう感じでした。
おまけに座席を仮予約して予約済座席で文字コラみたいなのを作られたり、社会的に迷惑な行為をするレベルのヘイトを向けられたこの作品。
もう3年経ったので観て感想言ってもフラットになるかな?と思っていざ観てみました。
先に言っておくとムービーナーズは一銭も貰ってないよ!っていうかライターや漫画家からよく「運営大丈夫なんですか?」ってレベルで案件も何もないです!(少なくともアムモ98運営になってから1回も無いです)
喪失の先を描く
これを見るまで「なんでタイトル変えたんだろう」と思っていたんだけど、いざ観てみるとこのタイトルは凄く正しいと思った。昔から理由は様々だかタイトルが変わる作品というのは珍しくも無いが、この作品に関しては意味が大きくある。
理由は簡単で、この作品は単なる作品を映像化しただけではなく映画でその先を描いていたのだ。


ワニが死ぬまでを描くのではなく、その死んだ後を描いているのだ。もしかしたら有名なのかもしれないが、これすら耳に入るには及ばず様々なノイズのせいで興味を持たせられなかったというのが正直な所。
物語は原作通りワニが死ぬまで若者たちのダラダラした日常を前半パートとし、ワニの死後100日後から始まる後半パートで構成されている。
この後半パートが完全オリジナルなのだが、これが意外な事だけど個人的には結構良かった。
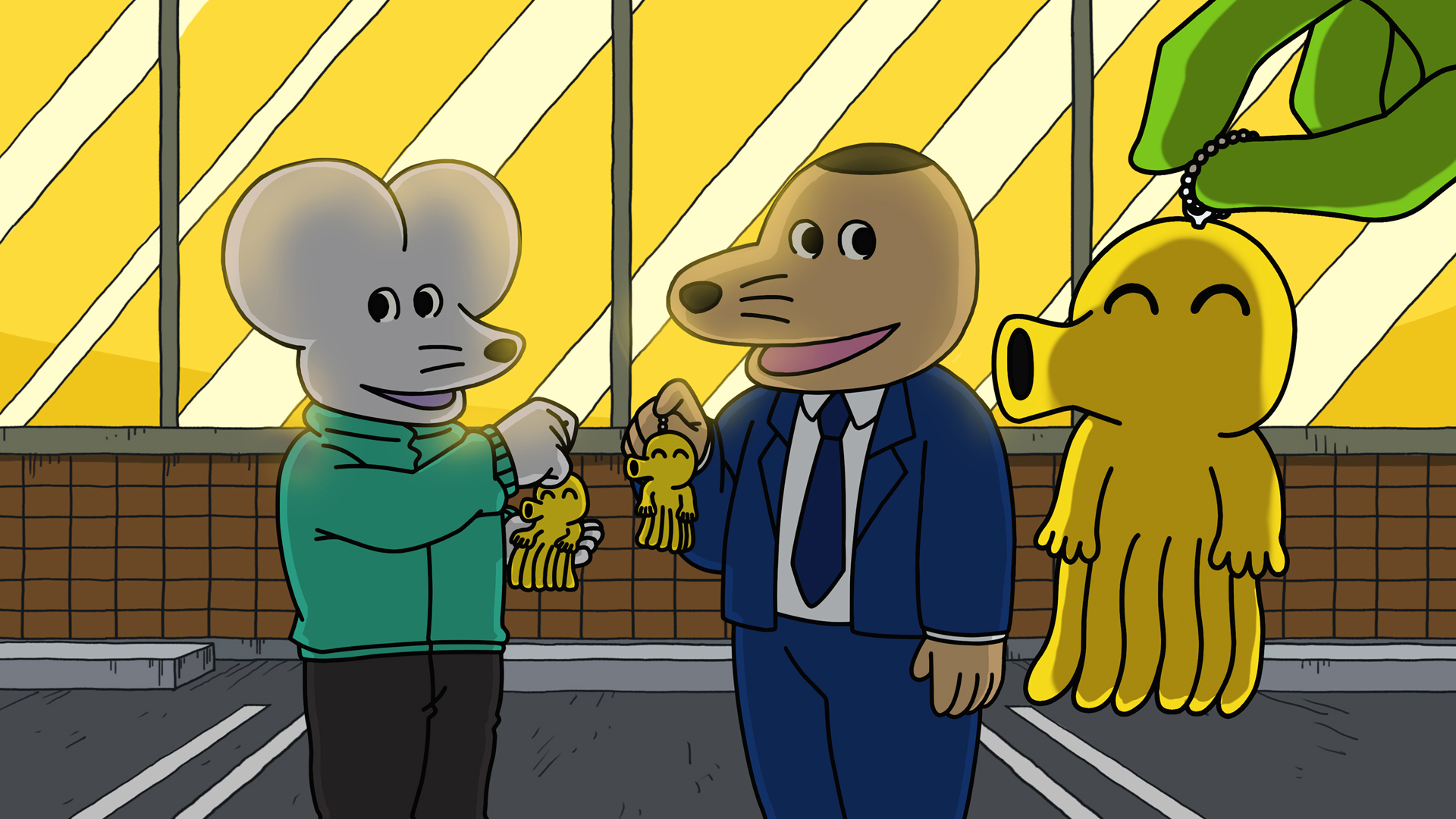
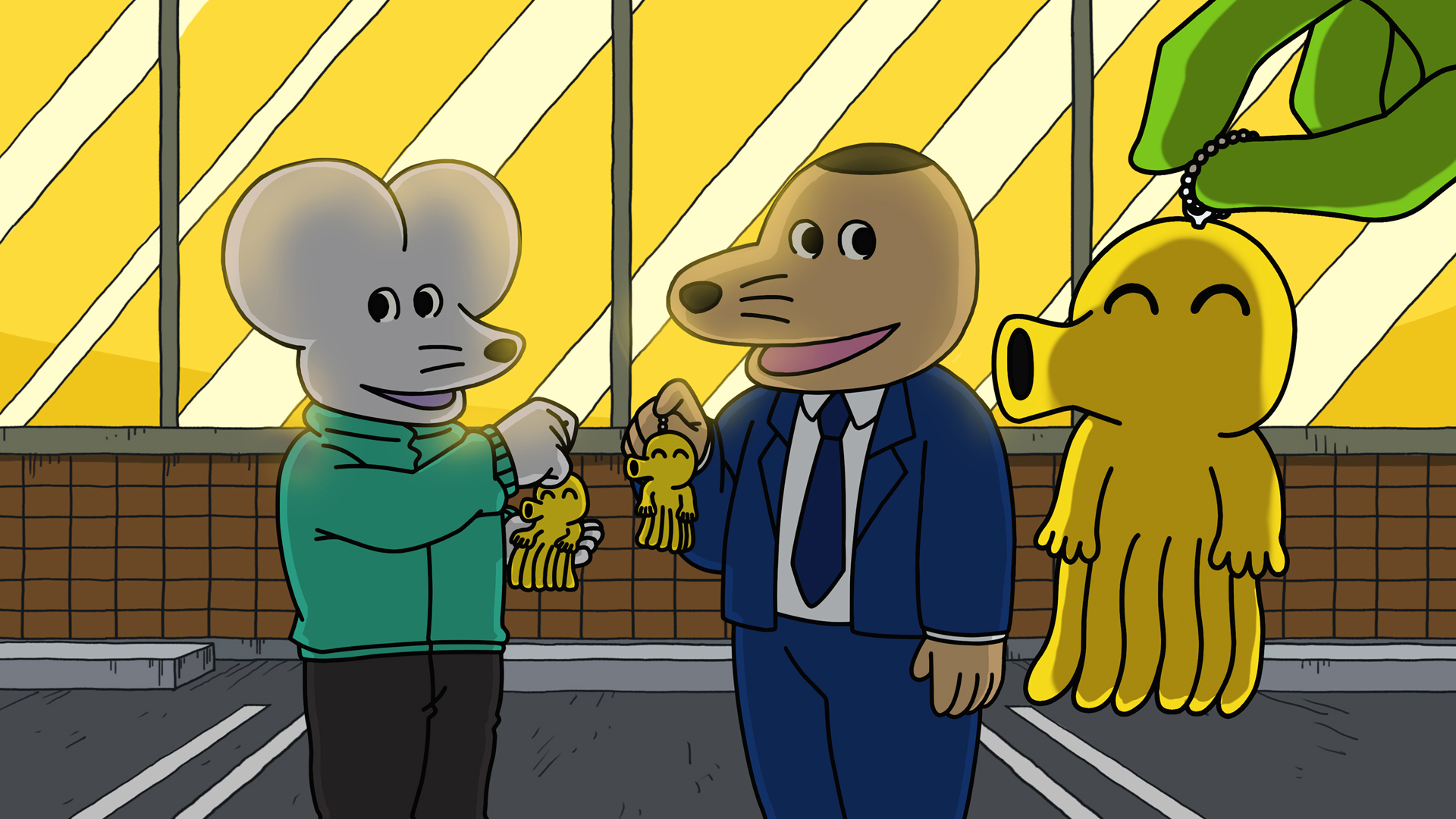
原作はワニが死ぬまで、追いかけてきた読者へ喪失を与えた段階で終了したのだが、それはあくまで読者側だけが喪失を味わいワニの友人たちは喪失を味わう前に物語は終了する。
つまり、喪失の物語ではあるがキャラクター達は喪失感を味わう前なのだ。
この映画版はその喪失感を味わい、友人や恋人としての関係が破綻とまでは言わないが、共通の友人の死という重すぎる話題のせいで関係性ぎこちなくなってしまった若者たちをこれでもかと見せてくる。
それぞれが傷を癒すでも舐めあうでもなく、お互いになんとなく距離を取り合うというのはなんだか妙なリアルさがある。
さまざまな掛け間違い
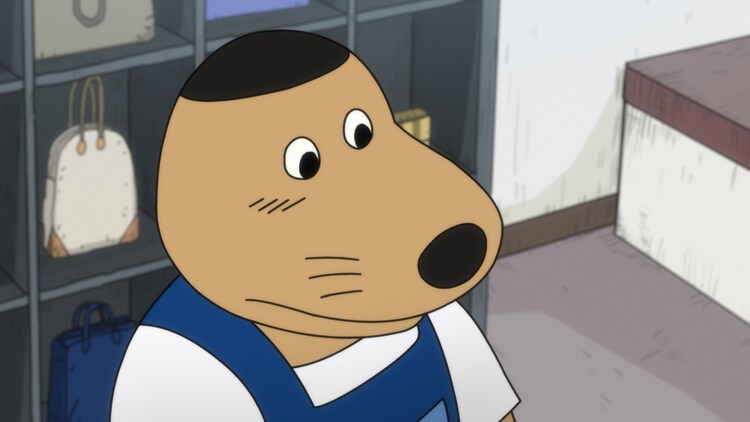
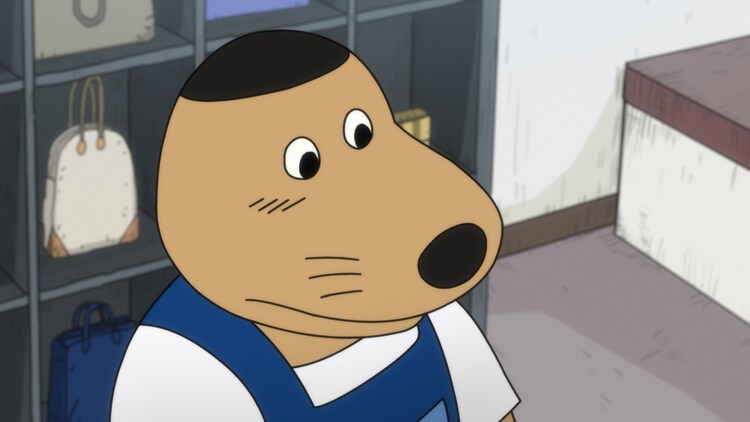
見た目が動物だから分かりにくいが、彼らは恐らく20代前半。
ぼんやりと何かになるために夢を見たり、ただ今を楽しんでいたのだから死などというネガティブなものはとても遠い場所にあったはず。彼らはまだ夢の世界に生きていたのだ。
描かれてはいないが中心人物であるワニ喪失の他にも、もっとリアルな現実を考える瞬間が訪れたのは想像に難しくない。死の軽い創作より外側にある死は何よりも現実なのだ。
それを空気感だけで描いていて、あぁ確かにこれは好みが分かれるしアニメとの相性はすこぶる悪い。
アニメをバカにしているとかではないのだが、アニメ的な文法の中ではこの空気感は出しにくく感じにくい。確かに、これをとって「退屈な映画」と取られてしまう場合はあると思った。
どちらかといえばこういうのは単館モノの邦画の文法に近いと思った。エンタメ性ではなく、ドラマ性をよりエッジ深めにする感じ。
よく出来ている出来てないではなく、武器の選択を間違っているように感じた。
映画版100ワニはこういった「武器の選択間違い」が沢山存在していて、これをより好意的に解釈するか悪意を持って解釈するかで味わい方が全然変わってくる。


特にやり玉にあがるのがカエルの存在で、まぁこいつがとにかくうざい。近くに居たら本当に嫌な奴で、空気を読めないだけならまだしも、突然「俺違います?」と返しにくい事まで言い出す始末。出来れば現実ではこのタイプの人間とは関わりたくない。
この映画のヴィランと言っていい。
でも、このヴィランという異分子が無理やり入り込んだおかげで段々と停滞していただけの関係性に変化をもたらしてくれる。
この辺も武器の選択の間違いというか、いくらなんでもカエルがうざすぎる。正直ここまでうざくなくていいと思った。いや、うざくないと彼の物語上の役割としては全く成立はしないのだけど、正直観ていて「いやだなぁ」と思ってしまうぐらいには嫌なキャラだ。はっきり言えばノイズに近い。存在が、というよりはキャラクター性がだ。
存在としては前述した通り関係性の修復に必要な存在で、もしかしたら彼らは二度と関係を戻せなかったかもしれない、戻ったかもしれないが10年後、20年後かもしれない。そう思わせるぐらい兎に角場をかき乱してくれる。
でも、こいつの印象が悪すぎて重要な役割のくせに物語の都合とかではなく「なんかまとまった」と感じるぐらい直視したくない。
せめてもっと一回り若いとか、うざいなりの理由がもう一つぐらい欲しかった。
ところどころ不出来ではあるけど…


武器の持ち間違いもそうなのだが、正直劇場作品としてはやや不出来な部分も多く、絶対的に肯定はしづらいと思った。
個人的に気になったのはきくちゆうき先生の世界観をリアルな邦画文法にしたときにノイズになる部分が多くて、例えば靴を履いてるキャラとそうでないキャラが並んで歩いているのなんかは明確なノイズだと思った。
真面目なシーンで裸足のキャラの横に靴を履いたキャラがいるのだ。それはもう気になってもしょうがない。
キャラデザの段階で映画用に色々共通化するべき場所にはじまり、いろんな部分がメディア化する際にあまり洗練されていないと感じた。
この辺は各々のリアリティラインによりそうなのだが、こういった小さい違和感から消していくのがメディア化だと思う。
公開時から言われていた『作画が悪い』に関しては割と気にならなくて、エンタメ作品では全然無いので作画を良くする理由があまり無い。確かに劇場作画というよりは、夕方のアニメの少し作画の良い回ぐらいなんだけど…この物語を描くには正直これで充分。
異様なヌルヌル作画にしてもそれはそれでノイズになりそう。


そういった意味で決して出来の良い作品ではないんですが、この作品の一番良いと感じたのは喪失の後に救済を用意してくれた事だ。
あのまま喪失を味わったであろうワニの友人たちをそのままにせず、死というどうしようもできない部分を改変するのではなく救いを用意したというのは作り手側の優しさを感じた。
そういった意味でこの作品がいかにヘイトを稼いでいたかというのがよく分かる。読み取れば悪くない部分も沢山あり、なんなら良い点すらポチポチあるのにその声は「ステマだ」「逆張り」などの言葉にかき消されてしまう。
実際、当時からこの作品を全肯定は少ないが一定数評価する人も居た。実際に今回改めて観てみるとそこまで悪くない。後世に残る名作とまでは言わないが、佳作ぐらいの仕上がりになっている。
どんな作品もフラットでいる必要は無いが、この作品に関してはフラットで観れて非常に良かった。
楽しめるかはかなり人による作品だけど、ネタにしたりコンテンツを雑に扱った作品でもなかったんだと安心出来た。